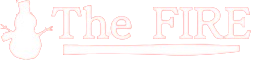「6000万円」という資産は大きな金額です。老後2000万円問題で取り上げられている2000万円の3倍の資産ですから、一見するとなかなか裕福な老後が迎えられそうです。
資産が5000万円以上になってくると、資金の使い方や運用方法は本人のリスク許容度によって大きく変わります。これは人生観の問題になってきます。
関連
まだまだ増やしたいと思う人は、起業して会社を立ち上げビジネスを拡大していくための初期費用にする人もいるでしょう。
人によっては資産運用で1億円、5億円と狙っていく人もいます。
関連
さて、6000万円という資産。筆者は30代であり、現在は富裕層クラスの資産額ですが「守りながら徐々に増やしていく」という方針をアッパーマス層の頃からとっています。
すでに6000万円という資産があるからこそ、この安定した運用が機能します。守りつつプラスを積み上げると複利の破壊力を実感できるかと思います。
今回はそんな6000万円、そもそもどうやってその資産を作っているのが普通なのか?
また運用するのであればどのような方法がベストプラクティスなのかを考察していきます。
-

-
【2024年】日本国内のヘッジファンド14社をおすすめ順にランキング形式で一覧にして紹介!
資産運用の世界に足を踏み入れることは、多くの人が避けて通れない道です。特に、貯金が1000万円を超えた瞬間、その資産の増加の遅さに心を痛める方も少なくありません。 このような状況に直面した際、資産運用 ...
続きを見る
具体的な資産運用についての記事:
6000万円の貯蓄がある人はどのような属性の人なのか?30代〜40代の割合はどれくらい?
そもそも6000万円という大金を蓄財できるのはどのような人なのでしょうか?
企業オーナー、ベンチャー役員や社員のストックオプション、一流アスリート、エリートサラリーマン、医師、相続などがメインになります。

日本全体で5000万円〜1億円未満の準富裕層は6%程度です。
当然、富裕層以上の世帯はさらに低い割合ですから日本の中でも相当な資産家であると捉えることができます。

参照:野村総研
以下は金融庁のデータですが、4000万円以上の金融資産を保有している世代は50歳以上となっています。
30代から40代で6000万円以上の資産を保有している方はごく少数であると言えますね。

企業オーナーや社長(中小企業/上場企業)
企業オーナーがまずは最初に挙がります。やはり「事業」というのは大きな金額が動きます。
企業オーナーは種類にもよりますが、事業を伸ばし、企業成長させていく過程で役員報酬も大きくしていくのが通常です。
もちろん税金は高くなります。
しかし、年商が軽々と10億円を超えるような企業を経営していれば、社長の年収は3000〜5000万円ほどに設定するのが私が出会った経営者達を見ると通常でした。
年収が5000万円であれば最高税率の領域に突入していますが、税後でも3年〜5年ほどあれば6000万円の資産には到達するかと思います。
よっぽどの浪費グセがない場合に限りますが。
本来は年収はもっと上げられますが節税方法が様々ありますので、あえて年収を抑えているとの話が多いです。
資産管理会社への配当などはよく聞きますね。
(注) 例えば「課税される所得金額」が7,000,000円の場合には、求める税額は次のようになります。
7,000,000円×0.23 - 636,000円= 974,000円
年収5000万円の場合は、50,000,000円×0.45 - 4,796,000円= 17,704,000円
所得税だけで2000万円近くが所得税で飛んでしまう世界線です。更に課税所得の10%である約500万円が住民税になります。
本当に「所得」をあげればあげるほど税金が大きくなる仕組みは辛いですね。5000万円を稼いでも半分程度しか手元に残らないという仕組みになっているのです。
所得で資産を積み上げるのであれば、度肝を抜くくらいに稼ぐ必要があります。多分、年収2,3000万円程度の人が一番負担を感じるゾーンなのではないでしょうか。
企業オーナーの強みとしては、やはり自社の株を持っていることでしょう。
会社を上場させる、M&Aで自身が保有する株を売却するなどで、自分の持つ株の価値を青天井に引き上げることができます。
やはり、自分で事業を起こすというのは夢のある話です。このオーナー経営者レベルになってくると資産は数億円は当たり前の世界になってきます。
事業を創造する、会社を成長させる、競争に勝つ、そして時流に乗る。相当な運がないと辿り着けない領域です。
しかし、6000万円であれば細々と経営している経営者さんでも10年、20年かければ容易にたどり着く水準ではあると思います。
ベンチャー企業勤務でストックオプション
ベンチャー企業で会社員として働いて、自社が株式市場に上場やM&Aした時に配られていたストックオプションの権利を行使して大金を得る人もいます。
有名な話にYouTubeがグーグルに買収された時に受付嬢がストックオプションを保有しており、なんと1億円以上のキャピタルゲインを獲得したという話もあります。
ストックオプション(英: stock option)とは、株式会社の経営者や従業員が自社株を一定の行使価格で購入できる権利[1]。従業員向けのものは英語ではemployee stock optionという。 ただし、法制度によっては対象を経営者や従業員に限定しない制度に組み込まれている。日本で2000年代に入って創設された「新株予約権」も、従来の転換社債の転換請求権、ワラント債の新株引受権、ストックオプションの権利をあわせて再構成されており[2]、従来の制度とは異なり権利付与の対象者の制限がなくなっている[3]。また、近年では信託を活用したストックオプション制度(信託型ストックオプション)も登場している[4]。 ここでは会社(企業)の役員や従業員が、一定期間内に、あらかじめ決められた価格で、所属する会社から自社株式を購入できる権利について述べる。
引用元:wiki
Googleに在籍していた社員も、IPOと共に多額の利益を獲得しました。
それが、Google初期に在籍し株長者となった多数の元従業員にとっての問題だ。Googleが新規株式公開(IPO)を行った2004年8月には、900人を超える従業員がにわかに大金持ちになり、彼らの資産総額はGoogle株の急騰とともに膨れ上がった可能性が高い。IPO時に85ドルだったGoogle株は、米国時間1月18日の終値で600ドル25セントを付け、600%以上の上昇率となっている。
ただし、ストックオプションとはベンチャー企業の創業初期メンバーなどでないとなかなか配られないものです。
ベンチャー企業に就職した時に、その企業が成功するかどうか、IPOやM&A以前の問題が山積みなのです。
非常に難易度の高い選択肢であるため、資産を積み上げるには相当なスピードが伴いますが、失敗した時に一文も手に残っていないことがほとんどです。
ストックオプションが配られる場合というのは、給与が低い代わり、という側面もあります。人生そんなに甘くありません。ストックオプションで6000万円を作るのは至難だと思います。
エリートサラリーマンや医者
エリートサラリーマンや医師も企業オーナーと同様高い年収で、数年積み上げれば6000万円は十分に達成可能な水準です。
例えば投資銀行勤務の人であれば、年収は1000万円から成功報酬で数億円といった部署まであります。成果給の部分が大きければ、その分大きな報酬機会を得られる可能性があります。
外資コンサルもパートナーまで昇進すれば年収はボーナスで変動もありますが、8000万円を超えてきます。
総合商社やメガバンクの社員であれば、海外駐在などを経て、40、50代に差し掛かる頃には6000万円程度の水準は確保できます。
しっかり運用を行えば、引退までに1億円以上は間違いなく資産形成ができると思います。ただ、外資系とは異なり質素な生活が求められるのもこの層です。
誤った資産運用を選ばない限りは、サラリーマンという待遇状ダウンサイドも少なく、かなりの資産形成が見込める属性とも言えます。
医師も同様に収入が高い職業です。総合商社の駐在待遇が日本で続いているパターンが筆者の周りでは多いですが、資産運用に積極的な人が沢山いるイメージもあります。
相続
親の相続などで大金を手にする人も多いでしょう。これは親が資産家だった場合に限ります。相当に運が良いパターンでしょう。
相続された方も、資産運用でさらに資産を大きくし、子供や孫へ財産を残してあげましょう。
金融知識がないのに大金を持ってしまった場合にIFAに相談した結果仕組み債を買ってしまい大損した話や、
大手の金融機関の窓口で投信を買ったら大暴落したなど悲惨な話も聞くので気をつけましょう。
6000万円でセミリタイアや完全リタイアは可能なのか? 資産運用だけで生活可能か?
どれくらいの水準で完全にリタイアできるかは、基本指標となるのは月々の生活費です。
この生活費を、資産を運用して3%程度のリターンで賄えるのであれば、それはリタイア生活可能であるという指標になります。
6000万円であれば、3%の運用ができれば年間180万円。税後で144万円です。144万円を12ヶ月で割ると12万円です。
12万円生活費があれば困らないという人であればという感じですね。
ちなみに二人以上世帯の消費支出の平均が金融庁資料で明らかにされています。ここでは消費支出313,057円。非消費支出が99,405円となっています。
合計で412,462円です。

月間412,462円の生活費を賄うには、どれくらいの資産が必要になりますでしょうか?
年額に直すと上記に12を掛け合わせて494万9,544円となります。
3%のリターンで上記の資金を賄うためには元本は1億6500万円が必要となります。1億円足りませんね。
仮に5%のリターンで生活費を賄うと考えても9900万円が必要となります。
ただ、上記の生活費から住居費を逆算すると1万8470円となります。
既に家を保有している前提の金額となります。東京の賃貸では20万円は住居費にかかりますので上記より更に多い金額が必要となります。
保守的に見積もると生活費にいくら必要なのかという点については以下で詳しく算出しています。
具体的な資産運用についての記事:
上記の記事では最低でもリタイアするために2.5億円以上の資産が必要という算定になります。
いずれにせよ6000万円では到底リタイアできそうにはありません。
<coffee break>金融資産5000万円以上の人達の日常
資産が5000万円以上ある人の日常とはどのようなものなのでしょう?
私自身も資産は5000万円を超えています。しかし、まだまだサラリーマンをしていますし資産運用も積極的にしています。
5000万円で独身であればリタイア可能なのですが、あまり贅沢もできません。
ちなみに東京に住んで子供2人を養っている筆者の1ヶ月の生活費は以下の通り年間860万円が必要となります。
高い家賃や子供の塾代などが嵩み夫婦で共働きしていないと厳しい状態です。

税後で3%の運用で上記の金額を賄うために必要な金融資産は3億6000万円が必要になります。4%運用前提でも2億7000万円が必要んなります。
上記の金額は都会でただ生きているだけという水準になってしまいそうなので、人生に遊びを取り入れるためにも、まだまだ資産の拡大を目指しています。
とある小説では「生きていくには足りないお金であり、死ぬには大きすぎる金額」とも形容されていました・・・。
ただ、若干の精神的な余裕は出てきています。例えば、以前は行かなかったロイヤルホストにいったり妻に少し高い鞄を買ってあげたりというプチ贅沢ができるようになりました。
少しは豊かになったなということを実感できています。しかし、まだまだであり筆者はさらに上を目指しています。
目標は持たないようにしています。いけるところまでいきたいです。
貯金6000万円あれば独身ならセミリタイアは可能?
上記はあくまで子持ちの家族を前提に話をしてきました。では独身の場合はどうでしょうか?
以下は独身の生活費です。現在2024年ではありますが、最新データとしてまとめられている2022年のデータは以下となります。
| 老後単身世帯 | |
| 食料 | 37,502 |
| 住居 | 12,739 |
| 水道光熱 | 14,743 |
| 家具・家事用品 | 6,012 |
| 被服費 | 3,149 |
| 保険医療 | 8,159 |
| 交通通信 | 14,600 |
| 教養娯楽 | 14,457 |
| 交際費 | 17,892 |
| その他 | 14,028 |
| 税金等 | 12,356 |
| 合計(月額) | 155,638 |
| 合計(年額) | 1,867,658 186万7,658円 |
これを現実的な数値に洗い替えると以下となります。都会の場合と地方の場合でわけました。

年間生活費は地方だと250万円、都会だと390万円となります。3%のリターンで上記の資金を賄うためには地方だと1億400万円、都会だと1億6000万円となります。
6000万円だとセミリタイアするのは、なかなか厳しいですね。
コラム:インフレは確実に進展している
さきほどは2022年のデータを用いました。
ちなみに2020年のデータだと以下となります。2年間で1万円以上の費用が増加しているのがわかりますね。
ちなみに2023年は更にインフレが進行しているので消費脂質は増加することが想定されます。
| 2021年データ | 2022年データ | |
| 食料 | 36,615 | 37,502 |
| 住居 | 12,383 | 12,739 |
| 水道光熱 | 12,915 | 14,743 |
| 家具・家事用品 | 5,326 | 6,012 |
| 被服費 | 3,196 | 3,149 |
| 保険医療 | 8,255 | 8,159 |
| 交通通信 | 11,983 | 14,600 |
| 教養娯楽 | 12,915 | 14,457 |
| 交際費 | 15,312 | 17,892 |
| その他 | 14,247 | 14,028 |
| 税金等 | 11,541 | 12,356 |
| 合計(月額) | 144,687 14万4,687円 |
155,638 15万5,638円 |
2023年は更にインフレが進行しているので消費脂質は増加することが想定されます。
ちなみに以下は新築マンション平均価格の推移は以下となります。バブルで歪んではいますが基本的には右肩上がりなのです。
そして、通貨の価値が落ち続けることはもう確定した未来なので、この傾向は変わることはありません。
常にインフレが進行していく前提でリタイアプランを組み立てていきましょう。
6000万円あったらどんな金融資産で運用をすべきなのか?
どんな運用をすべきかという話ですが、私の場合はこれまで実施してきた運用と歴史に照らし合わせた投資しかしないので、結局株式投資という話になってしまいます。
古今東西資産運用の王様「株式投資」
なぜ株式投資かというと、それは過去の歴史がそのリターンを証明してしまっているからです。
STOCK:株
BONDS:社債
BILLS:国債
GOLD:金
USD:現金

1802年から続く歴史で、株式が圧倒的に他資産をアウトパフォームしています。
もちろん、個人で株式投資を行うのはリスクが高いです。株式投資はハイリスクハイリターンです。
→ 投資におけるリスクとは!?ハイリスクハイリターン投資よりローリスクミドルリターン投資を狙おう!
6000万円で株式投資をするのであれば、1000万円くらいにとどめて、残りは他でもっと安全に運用することをお勧めします。
個別株投資は遊びと捉えた方が良いです。株式投資でお金持ちになった人をメディアなどは囃し立てます。
しかし、生存者バイアスがかかっており下を見ると屍がたくさん転がっているはずです。
→ 相場歴10年を超える筆者が「個別株は難しい?」「個別株は無理ゲー、ギャンブルだからやめとけ」等の意見に思うこととは?悲惨な結果でもうダメとなる前に読んで欲しい。
株式投資で人生一発逆転、と意気込んでいる人はあまりにも相場を理解していないのだと思います。
投資歴の長い結果を出しているプロの投資家ほど「株式市場は何が起こるかわからない」と言うものです。
投資信託
さて、狙いを株式投資に定めたものの、個別株は危険すぎると述べました。
ここでやはり次に検討するのは投資信託でしょう。投資信託にはアクティブ、インデックスの2つがあります。

アクティブとインデックス、どちらを選べば良いのでしょうか?
| 分類 | 平均5年累積リターン |
| パッシブ型全ファンド | 22.60% |
| アクティブ型全ファンド | 9.70% |
| パッシブ型日本株ファンド | 40.00% |
| アクティブ型日本株ファンド | 30.90% |
| パッシブ型先進国株ファンド | 37.00% |
| アクティブ型先進国株ファンド | 12.00% |
| パッシブ型新興国株ファンド | 15.20% |
| アクティブ型新興国株ファンド | 12.80% |
| パッシブ型グローバル株ファンド | 32.60% |
| アクティブ型グローバル株ファンド | 8.20% |
5年で見ると差は明らかで、インデックス型(パッシブ)が平均累積リターンが22.6%になっています。年利回りは4%程度です。
購入するのであれば、インデックス型の投信を選ぶのが正解になってくるでしょう。
以下はシャープレシオですが、こちらもインデックス型が優秀です。
| 分類 | 5年シャープレシオ平均 |
| パッシブ型全ファンド | 0.40 |
| アクティブ型全ファンド | 0.20 |
| パッシブ型日本株ファンド | 0.50 |
| アクティブ型日本株ファンド | 0.40 |
| パッシブ型先進国株ファンド | 0.47 |
| アクティブ型先進国株ファンド | 0.23 |
| パッシブ型新興国株ファンド | 0.24 |
| アクティブ型新興国株ファンド | 0.20 |
| パッシブ型グローバル株ファンド | 0.44 |
| アクティブ型グローバル株ファンド | 0.17 |
リスクリターンの観点から、パッシブ型投信を選んで運用するようにしましょう。
【ブログ随時更新】飛躍の2024年!今買いの一番儲かる投資信託銘柄はどれ?「安全」且つ「これから上がる」個人投資家が買うべき高利回りファンドを徹底調査!
インデックス投信だから安心というのも迷信
2010年代一貫して米国のS&P500指数などのインデックスが上昇したことによりインデックス神話が産まれています。
インデックスを購入しておけば安心だという考えを持っている方もいらっしゃいます。
しかし、これは非常に危険な考えです。大体、このように皆が考えた時が相場の天井なのです。
S&P500指数は以下の通りリズムを持って停滞期と上昇期が分かれています。あくまで長期的な平均リターンが7%なのです。

1980年からの40年間、低金利政策でブーストした分のつけを払わされる局面に来ています。

2010年代に世界中の各中央銀行が金融緩和と財政出動をした結果、40年ぶりの大きなインフレが発生しています。
特に2020年のパンデミック以降の金融緩和は異常なもので、世界に紙幣が溢れるという事態が発生しました。
結果として需要が極大に達し、さらにパンデミックのせいでサプライチェーンが混乱して需要増と供給減のダブルパンチで高インフレとなっています。
そのため、米国の中央銀行FRBや欧州の中央銀行ECBを中心として金融引き締めで金利を引き上げて景気を冷ましています。結果として株価を引き下げる動きとなっています。ただ、インフレは高止まりしておりおさまる気配はありません。
今後、さらに実体経済が景気後退していくことによって株価は長期低迷のフェーズを迎える確度が高くなっています。
そして、一時は151円まで急伸し、現在2024年1月現在141円まで進展しているドル円が下落すると円建のリターンも毀損します。株価が20%下がり、ドル円が10%下落するだけで単純計算で30%以上の下落となりますからね。
ここからインデックス投資をするのは注意をはらったほうがよいでしょう。加えて、グーグルやアマゾンなどの米大手テクノロジー企業群であるGAFAMの成長率も頭打ちし、低成長時代を迎えています。
これらの企業が2000年から米国相場を牽引してきました。しかし、今後はかなり厳しく、”主役不在”の米国株が過去と同様のリターンを提供してくれるとは筆者は思えません。
米Google(グーグル)の持ち株会社、Alphabet(アルファベット)は米国時間2023年2月2日、2022年10~12月期の決算を発表した。売上高は前年同期比0.9%増の760億4800万ドル(約9兆7900億円)だったものの、純利益は同34.0%減の136億2400万ドルに落ち込んだ。減益は4四半期連続となる。1株当たり利益は1.05ドル(前年同期は1.53ドル)だった。いずれも市場予想を下回り、同社の株価は時間外取引で一時6%下落した。
ヘッジファンド投資
インデックスも危ないというのであれば、何に投資をすればよいのでしょうか?そこで注目されているのが世界の機関投資家や富裕層がこぞって投資しているヘッジファンドです。
ヘッジファンドとは、投資家から私募ファンドという形式で資金を募ります。
上記で紹介した投資信託は「公募ファンド」であり、積極的にメディアなど宣伝活動を行い投資家を少額から集めています。
ヘッジファンドは紹介がベースになっています。なかなか情報が取れません。最低出資額も日本国内では1000万円からであることが多く、その敷居も高いです。
→ 富裕層向けの金融商品「ヘッジファンド」と「投資信託」の違いをわかりやすく解説!両者のメリットとデメリットを比較しながら検証する。
ヘッジファンドは募った資金を活用して、株式市場、コモディティ、債券などなど、様々な市場で高いリターンを、投資の専門家であるファンドマネジャーが目指していきます。
結果としてヘッジファンド全体の成績(濃青)としては以下の通り、安定したリターンをあげています。
株式市場が軟調な局面でも下落を抑制して、上昇局面も取ることで右肩上がりの安定したリターンを具現化しているのです。

リターンもさることながら損失を抑えて安定的に資産を増やすのがヘッジファンドの特徴といえます。
そのため、世界の富裕層や年金基金、保険会社などからの信用を集め運用残高も年々上昇しています。

ヘッジファンドはファンドによって戦略が異なりますし、実績もそれぞれです。
筆者は世界一の投資家であるウォーレン・バフェット氏の哲学をもとに選定基準を定めています。その基準とは運用歴が長く、マイナスを出した年が少ない、の2点です。
バフェット氏が世界有数の大富豪になれたのは複利効果による恩恵が大きく、その複利効果を得るには可能な限りプラスリターンを積み上げる必要があります。
バフェット氏の実績は運用開始から35年はマイナスなし、50年でマイナスの年は2回のみと、抜群の運用成績でした。

株式投資の巨星:ウォーレン・バフェットの投資哲学とバークシャー・ハサウェイの興隆
例えば私が投資をしているヘッジファンドは株式投資に資産を投じています。平均年利回りも10%を超える実績があります。(年によってはそれ以上も)
複利効果も効きますので、時が経てば経つほど資産増加の勢いは増していきます。運用チャートのイメージとしては世界最大のヘッジファンドであるブリッジウォーターと非常に似ています。面談を行うことで見ることができます。

関連:世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーターアソシエイツを解説。帝王レイ・ダリオの投資哲学とは?
ブリッジウォーターは1000億円以上の資産を有していないと投資することは出来ないので、個人投資家には手が届きません。
しかし、筆者が投資しているBMキャピタルは同様の水準を日本の個人投資家も投資できるように受け入れています。


バリュー株投資という最大ドローダウン(損失額)を抑えつつ、安定的に資産を増やしていく哲学に納得し、また実績が伴っていたことから投資に踏み切りました。
以下ではヘッジファンドを選ぶ上での注意点などもまとめていますので、参考にしてみてくださいね。
-

-
【2024年】日本国内のヘッジファンド14社をおすすめ順にランキング形式で一覧にして紹介!
資産運用の世界に足を踏み入れることは、多くの人が避けて通れない道です。特に、貯金が1000万円を超えた瞬間、その資産の増加の遅さに心を痛める方も少なくありません。 このような状況に直面した際、資産運用 ...
続きを見る
6000万円で組むおすすめのポートフォリオ
ポートフォリオの割合ですが、私であれば、以下の割合で持つと思います。
- ヘッジファンド:4000万円
- 個別株:500万円
- 現金:1500万円
個別株を500万円持つのは、来たる老後に向けてマーケットに触れることで金融リテラシーの向上、また世界経済の流れを学び自身の生活に生かしていくためです。
先ほどお伝えした通り、現在はインデックスを持つ環境ではないのでインデックス投資はいれていません。
あくまでしっかりと下落した後に現金1500万円を出動させて買いに行く予定です。
具体的な資産運用についての記事:
まとめ
資産6000万円とはどのようなお金なのか、運用するとしたらどのような資産が良いのかを紹介しました。
資産運用は一つの旅であり、取り組み次第では人生が大きく変わるものです。積極的に運用を行なっていきましょう。
-

-
【2024年】日本国内のヘッジファンド14社をおすすめ順にランキング形式で一覧にして紹介!
資産運用の世界に足を踏み入れることは、多くの人が避けて通れない道です。特に、貯金が1000万円を超えた瞬間、その資産の増加の遅さに心を痛める方も少なくありません。 このような状況に直面した際、資産運用 ...
続きを見る