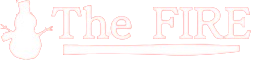前回、ヘッジファンド型の投資信託「ダブルブレイン」についてお伝えしました。
→ 野村證券が販売するヘッジファンド型運用の投資信託「ダブルブレイン」を投資家目線で評価!ファンド・オブ・ザ・イヤー2020受賞の評判のファンドを分析。
ダブルブレインについては「ダブルブレイン(ブル)」と「ダブルブレイン(マイルド)」というシリーズが登場しています。
イメージとしては以下となります。
ダブルブレイン(ブル)はリターンが高い代わりにリスクも高く、ダブルブレイン(マイルド)はリターンが低い代わりにリスクも低く設計されています。
今回は三つのダブルブレインを横並びで比較しながら検討していきたいと思います。
ダブルブレインの2つの戦略
復習にはなりますが、ダブルブレインには2つの戦略があります。
詳しくはダブルブレインの記事でお伝えしています。
第1戦略:リスクコントロール戦略
1つはリスクコントロール戦略です。リスクコントロール戦略は価格の値動きを察知してポジションを柔軟に変化させるという戦略です。

第2戦略:トレンド戦略
2つ目の戦略はトレンド戦略です。トレンド戦略は相場の流れをよんで、市場の上昇局面でも下落局面でも利益獲得を狙う投資戦略です。
市場が上昇する局面では対象資産を購入して、逆に市場が下落する局面では対象資産を空売りして収益獲得を狙います。

3つのシリーズの戦略の投資比率
これら二つの戦略を組み合わせてダブルブレインは運用がなされています。以下はそれぞれの戦略の組入比率です。
| ブル | 通常盤 | マイルド | |
| リスクコントロール戦略 | 86% | 86% | 75% |
| トレンド戦略 | 14% | 14% | 25% |
ブル型と通常盤のダブルブルはリスクコントロール戦略の比率が高くなっています。
マイルド戦略でも75%はリスクコントロール戦略の比率が4分の3となっています。
先物や空売り含むリスクコントロール戦略を3つのダブルブレインで比較
まずはリスクコントロール戦略の比較をしていきましょう。
以下は3つのシリーズの現在のポートフォリオの比較です。パーセンテージは投資元本に対する比率です。
比率が100%を超えているということは先物をつかってレバレッジをかけているということを意味しています。
| ブル | 通常盤 | マイルド | |
| 株式 | 153.8% | 76.9% | 38.5% |
| インフレ連動債 | 34.2% | 17.1% | 8.6% |
| クレジット | 151.6% | 75.8% | 37.9% |
| 債券・金利 | 95.6% | 47.8% | 23.9% |
| コモディティ | 41.8% | 20.9% | 10.5% |
ご覧いただければ分かる通り、ブルは全ての資産が通常盤の約2倍となっています。
一方、マイルドは全ての資産が通常盤の約半分となっています。
つまり、特段相場に対する考え方は変わらないけども、取っているリスク量が異なるということになります。
コラム:クレジットとは?
先ほどの構成資産の中で株式やインフレ連動債(インフレに連動する形で上昇する債券)、債券、コモディティ(金や原油等)は理解できた方が多いと思います。
しかし、クレジットについては初めて聞いた方が多いと思いますのでみていきましょう。
クレジットというのは証券会社の説明では以下の通りとなっています。
「信用リスク(資金の借り手の信用度が変化するリスク)」を内包する商品(クレジット商品)を取引する市場の総称です。クレジット商品には、貸出債権や社債、CPのほか、様々な信用リスクを加工して証券の形で売買する「証券化商品」や、信用リスクを原資産とする派生商品(デリバティブ)である「クレジット・デリバティブ」などがあります。
参照:カブドットコム證券
一番わかりやすいのは貸出や社債ですね。つまり企業に資金を貸し出す代わりに利息をもらうことができる投資手法ということになります。
トレンド戦略を3つのダブルブレインで比較
トレンド戦略はロング(買い)とショート(売り)が交錯する戦略です。そのため、ロングとショートを相殺したネットで比較していきたいと思います。
例えば、ロングの比率が50%でショートの比率が20%であればネットは30%となります。
以下はシリーズ毎のネットの比率です。リスクコントロール戦略と同じくブル型は通常盤の2倍のサイズ、マイルド型は通常盤の半分のサイズとなっています。
ただ、投資している比率としては同じ構成となっています。
| ブル | 通常盤 | マイルド | |
| 株式 | 211.6% | 105.8% | 52.9% |
| 通貨 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| クレジット | 181.2% | 90.6% | 45.3% |
| 債券・金利 | -156.6% | -78.3% | -39.15% |
| コモディティ | -49.0% | -24.5% | -12.2% |
2つの戦略と構成比率から導き出されるポートフォリオ
今までのポイントをまとめると以下となります。
| ブル | 通常盤 | マイルド | ||
| 戦略比率 | リスクコントロール比率86% トレンド戦略14% |
リスクコントロール比率86% トレンド戦略14% |
リスクコントロール比率75% トレンド戦略25% |
|
| リスク コントロール戦略 |
株式 | 153.8% | 76.9% | 38.5% |
| 通貨 | 34.2% | 17.1% | 8.6% | |
| クレジット | 151.6% | 75.8% | 37.9% | |
| 債券・金利 | 95.6% | 47.8% | 23.9% | |
| コモディティ | 41.8% | 20.9% | 10.5% | |
| トレンド戦略 | 株式 | 211.6% | 105.8% | 52.9% |
| 通貨 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| クレジット | 181.2% | 90.6% | 45.3% | |
| 債券・金利 | -156.6% | -78.3% | -39.15% | |
| コモディティ | -49.0% | -24.5% | -12.2% | |
上記を構成比率まで加味して導き出されるそれぞれのシリーズの構成比率は以下となります。以下の比率は元本に対する比率です。
| ブル | 通常盤 | マイルド | |
| 株式 | 161.9% | 80.9% | 40.5% |
| 通貨 | 29.4% | 14.7% | 7.4% |
| クレジット | 155.7% | 77.9% | 38.9% |
| 債券・金利 | 60.3% | 30.1% | 15.1% |
| コモディティ | 29.1% | 14.5% | 7.3% |
かなり株式に対して強気のポジションになっていますね。
3つのダブルブルのリターンを比較
では肝心なリターンの比較をみていきましょう。
赤:ダブルブレイン(ブル)
青:ダブルブレイン
緑:ダブルブレイン(マイルド)

ダブルブレインとダブルブレイン(マイルド)とダブルブレイン(ブル)のリターンの比較
当然ながら、リターンは「ブル」「通常盤」「マイルド」の順番となると思いきや、マイルドが一番マシです。相場の下落が大きすぎるので、マイルドのディフェンス力が輝いています。
ただ、投資におけるリスクである値動きの激しさは「ブル」「通常盤」「マイルド」の順番となっています。
→ 投資におけるリスクとは!?ハイリスクハイリターン投資よりローリスクミドルリターン投資を狙おう!
ダブルブレインシリーズの今後の見通し
では今後の見通しについて考えていきましょう。もう一度3つのダブルブレインのポートフォリオを見ていきましょう。
| ブル | 通常盤 | マイルド | |
| 株式 | 161.9% | 80.9% | 40.5% |
| 通貨 | 29.4% | 14.7% | 7.4% |
| クレジット | 155.7% | 77.9% | 38.9% |
| 債券・金利 | 60.3% | 30.1% | 15.1% |
| コモディティ | 29.1% | 14.5% | 7.3% |
非常に多くのポーションを株式に投じていることが分かります。
急激に株式のポジションを増やしています。かなり上がってしまってから株式のポジションを増やしているので後手にまわっていますね。
ただ、既に高金利が継続しインフレも続いたことで遂に米経済も限界を迎えています、以下の通り利益予想は低下しています。

ここからは純利益に連動する形で株価は下落していくことが想定されます。ダブルブレインはヘッジファンドとして決してうまい運用を行えているとはいえませんね。
まとめ
ダブルブレインには積極的にリターンを狙うブル型と安定的なリターンを狙うマイルド型が存在している。
リターンは「ブル型」「通常盤」「マイルド型」の順番になっているが、リスクも「ブル型」「通常盤」「マイルド型」の順番になっている。
ただ、ポートフォリオは債券偏重になっており、今後リターンを狙う上で足枷になることが考えられます。
ヘッジファンド型の運用で高いリターンを狙うのであれば、更に良い選択肢を検討することをおすすめします。
以下では筆者の観点でおすすめできるおるアタナティブ投資先を含めてランキング形式でお伝えしていますので参考にしていただければと思います。