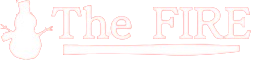私募ファンドであり情報が中々表に出ない故に、ヘッジファンド投資を迷っている方は多いかと思います。
それもそのはず、欧米ではハーバード大学基金が投資するなどメジャーな投資先ととなっていますが、日本では近年まで超上流階級の間でしかヘッジファンド投資の話は聞くことができませんでした。
しかし、現在は2020年以降の投資ブームなどもあり、徐々にヘッジファンド投資の知名度が上がってきました。
今回はそんなヘッジファンド投資がおすすめできる投資先なのか、はたまたおすすめできたものではないのかを考えていきたいと思います。
関連記事)【2024年】日本国内のヘッジファンド14社をおすすめ順にランキング形式で一覧にして紹介!
そもそもヘッジファンドとは?
「ヘッジファンド」とは市場に連動するインデックスファンド、または指数のアウトパフォームを目指すアクティブファンドとは異なり、最大限にリターンを狙う「絶対収益型」のファンドとなっています。
これだけ聞くと、非常にリスクの高い投資先なのではないかと思ってしまいますが、実際は堅実に運用するヘッジファンドも存在しますし、積極的にレバレッジをかけるヘッジファンドもあり様々です。
ヘッジファンドの一番の特徴としては、株式相場が下落しても、ショート戦略でリターンを狙ったり、上昇相場ではレバレッジをかけるなど市場に柔軟に対応して利益を獲得していく点です。
つまり、下落耐性が強いことを意味します。歴史を振り返っても実際にヘッジファンドは市場暴落を回避し指数をアウトパフォームしてきました。
インデックスファンドは暴落時もホールドし続けなければならず、基本的には損失を受け入れ上昇をとにかく待つ必要があります。
過去は上昇してきましたが、永続的に上昇すると考えるのも楽観的思考が過ぎると思います。

ヘッジファンド投資でどれくらいリターンが獲得できるかはそのヘッジファンドのファンド(ポートフォリオ)マネジャーの腕次第であり、投資先を選定する際には、マネジャーの経歴や実績をしっかりと確認する必要があります。
誰もが株式相場の(メジャーリーガーの)大谷翔平や吉田正尚のような「結果を出す人材」に自分の大切な資金は任せたいですよね。
「ヘッジファンドとは?」という点を深掘りした記事は以下になりますので参考にしてみてください。
-

-
【2024年】日本国内のヘッジファンド14社をおすすめ順にランキング形式で一覧にして紹介!
資産運用の世界に足を踏み入れることは、多くの人が避けて通れない道です。特に、貯金が1000万円を超えた瞬間、その資産の増加の遅さに心を痛める方も少なくありません。 このような状況に直面した際、資産運用 ...
続きを見る
ヘッジ ファンド投資をやってみた筆者があえて考えるおすすめしない理由
さて、筆者がヘッジファンドへ投資しているので、多少バイアスがかかってしまっているかと思いますが、あえておすすめしない理由を挙げていきたいと思います。
ヘッジファンドへ投資しているからこそ、リアルな情報であり、投資していない人の批判よりはだいぶマシだと思います。
ヘッジファンドをおすすめしない理由①:商品内容が複雑で特徴(リスク)を理解しづらい
ヘッジファンドをおすすめしない理由の一つとしてよく聞く話が、投資戦略が複雑で理解できないなどが挙げられます。しかし、筆者個人としてはそこまで深く戦略について理解する必要がないと思います。
大事なのはリターンですからね。
まずヘッジファンドの運用戦略は多岐に渡ります。以下は一例ですが、投資を始めたばかりの投資家には聞き慣れない言葉が多いと思います。
- グローバルマクロ戦略
- 株式ロング・ショート戦略
- イベントドリブン戦略
- マネージド・フューチャーズ戦略
- 債券リラティブバリュー戦略
- ディストレスト証券戦略
- 転換社債戦略
しかし、戦略を選んでヘッジファンドに投資するというとかなり玄人的な投資です。
筆者の意見になってしまいますが、実績ベースで堅実なリターンを長年継続しているヘッジファンドを選べば良いかと思います。自分で運用するわけではないですからね。
相場を読んでどのヘッジファンドに投資をするなど、そういう話ではないはずです。むしろファンドマネジャーが相場の状況に合わせて戦略を変えていくので、投資家はそこまで戦略を深く知る必要がないというのが本質です。
ヘッジファンドをおすすめしない理由②:リスクを知らずに投資してしまう
ヘッジファンド投資のリスクを知らずに投資してしまい大損をしてしまうのでおすすめしない、という理由も聞きます。
投資はそもそもリスクがあり、投資をする際にはしっかりヘッジファンドの担当者なりに質問をぶつけるようにしましょう。
例えば、FX取引でレバレッジ運用をしており突発的なニュースで大きく損失が出る可能性があるなど、そういった点は把握すべきですが、筆者としてはFXで運用するヘッジファンドというのは聞いたことがありませんし、そもそもヘッジファンドのほとんどは堅実運用です。
ハイリスクハイリターン投資のヘッジファンドは、あるとは思いますが、基本的には避けた方が良いと思います。
「ヘッジファンドはおすすめしない」というのは、主語があまりにも大き過ぎると思われます。「レバレッジ取引を多用するヘッジファンドはおすすめしない」であれば筆者も大賛成です。
ただ、2022年の債券の下落で分かる通り、どんなに安全と言われる運用でもリスクは存在しますので、まずはレバレッジファンドを避ける、そして実際に投資をするファンドのリスクはしっかり把握するようにしましょう。
ヘッジファンドをおすすめしない理由③:詐欺案件に投資してしまう可能性
ヘッジファンドは基本的に「私募ファンド」形式で投資家の資金を運用しています。
つまり、公募投信とは異なり、楽天証券やSBI証券などを通して購入することもできず、知人の紹介などがメインになってきます。
情報開示も限られており、日本でも有名な柳下氏も私募ファンドについて言及されていますが、一般に募集することはありません。

しかし、例えば上記でも触れましたがFXファンドなど、一般投資家から資金を集める理由がわからないようなファンドもあり、また単純にポンジスキームである場合もあり、見極めが難しいです。
ヘッジファンドをおすすめできないというより、ヘッジファンドを名乗るポンジスキームに引っかかる可能性が多少なりともあるため、ヘッジファンドをおすすめしないという声があるのは筆者もある程度は理解できるところです。
やはり、ファンドマネジャーなどのエビデンスのある経歴などをしっかり確認するのは重要と言えるでしょう。
ヘッジファンドをおすすめしない理由④:ヘッジファンド選び失敗!ファンド自体が大損してしまう
ヘッジファンドに投資したらそのヘッジファンドが損失を出してしまうのでおすすめしないという話もありますが、ヘッジファンドの選定ミスか、長期前提での投資なのに半年など短期の成績を見て批判する声もあったりと様々です。
ヘッジファンドを選ぶ基準を明確にする必要があります。筆者の場合はレバレッジをかけるようなファンドはまず選ばず、とにかく複利運用で資産を増やしたいので、自ずと選ぶファンドは損失をミニマイズできるファンドになります。
筆者の基準を具体的に挙げると以下の通りです。
- ファンドマネジャーの経歴(優秀なヘッジファンドのマネジャーはいずれも超高学歴です)
- 10年以上の堅実なリターンを計上している
- マイナスを出さない運用哲学
- レバレッジをかけるタイプのファンドではないこと
上記4つを念頭にヘッジファンドを選べば、大きく外すことはないと思われます。
コラム〜ヘッジ ファンド投資でリタイア生活は可能か?
ヘッジファンドでリタイア生活は可能かというと、これもまた主語があまりにも大きすぎますよね。筆者の感覚になりますが、優秀なヘッジファンドで2億円以上の資金を運用すれば、リタイア生活は可能だと思います。
そもそもリタイア生活、最近ではFIREと呼ばれていると思いますが、そう簡単に実現できるものではありません。
しかし世の中のFIRE希望の方々は5000-1億円でFIRE達成可能と考えているようです。
さらに、FIREするために必要だと思う資産額を質問すると、ボリュームゾーンは「5000万円以上~1億円」で54.2%、続いて「~5000万円」(19.6%)、「~2億円」(11.4%)が続く結果に。平均額は、1億900万円だった。
筆者は最低でも2億円は必要だと考えています。5000万円でFIREを志すと聞いた時は開いた口が塞がりませんでした。絶対に無理です。
純金融資産2億円〜3億円以上あったらサラリーマンもセミリタイア(FIRE)生活可能?何年暮らせる?投資・運用はまだ必要なのかなどの疑問を一挙に解消
優秀なヘッジファンドであれば、年率20%程度のリターンを出してしまいますが、2億円あれば4000万円のリターンとなりますので、かなり余裕を持ってリタイア可能でしょう。
しかし、年率20%出すようなヘッジファンドは今のところ日本には見当たりませんし、コンスタントに10%出すファンドも稀有です。
大体は派手なリターンを出した翌年には大きくマイナスを出したりとボラティリティの高い取引を行うヘッジファンドも少なくありませんので、FIRE生活を志すのであれば、堅実な運用先を探すに限ると思います。堅実な運用ですので、それなりに元本は必要になります。
ヘッジファンドで失敗しないためのポイント
余剰資金で資産運用する
ヘッジファンドに限らず、投資全般に言えることですが有金全てを投資資金にするのはリスクが高いと思います。
特に個別株やテーマ型の投資信託、またはレバレッジ投信にフルインベストする人をたまに見かけますが、やっていることは博打です。
生活防衛費は必ず残して、残りを投資に充てるようにしましょう。例えば、月20万円の生活費であれば、1年半分は残しておきたいところですので360万円程度はキャッシュで残しておきたいところです。
ヘッジファンドによりますが、ロングショート戦略などリスク高めのヘッジファンドであれば投資資金の30%程度に抑える、債券型やバリュー投資型であれば、70%に引き上げるなど工夫をしていきましょう。
信頼できるヘッジファンドに依頼する
信頼できるヘッジファンドをどのように見極めるかですが、これは少し難易度が高いです。
筆者は必ずファンドマネジャーの経歴をしっかり見るようにしています。ウォーレン・バフェット氏はコロンビア大学、レイダリオ氏はハーバードビジネススクール、メダリオンファンドのシモンズはMITなど、優秀なファンドマネジャーはいずれも名門大学を卒業しています。
名門大学くらい卒業しているレベルの頭脳を持ち合わせているのが当たり前の世界です。経歴が全てではありませんが、経歴でフィルターをかけることで、ポンジスキームのファンドなどを回避する確率が跳ね上がります。
経歴が綺麗な人は、犯罪に手を染めるという発想すらなかなかありませんし、悪事を働く方がもはやコストが高いです。
例えば、筆者が投資をしているBMキャピタルのファンドマネジャーは東大卒の英国バークレイズで経験を積んだ方であり、相当に信頼を置いた上で投資を実行しました。

>>> 和製国内ヘッジファンド・BMキャピタルの実態を徹底的に暴く。
コラム〜日本最大のヘッジ ファンドとは?
世界最大のヘッジファンドは2023年時点でレイダリオ率いるブリッジウォーターとなっていますが、日本最大のヘッジファンドと言われているのは、農林中央金庫(JAバンク)です。
市場運用資産規模が60兆円となっており、国際分散投資を実施しています。

JAバンク・JFマリンバンクの資金を運用していることで、ヘッジファンドというと少し違和感はありますね。自社バンクの資金を運用している金融機関というイメージです。
本格派のヘッジファンドで規模が大きいファンドといえば筆者はBMキャピタルが思い浮かびます。同社は200億円程度の運用額であり、まだまだ伸び代十分で将来が楽しみな存在です。
ヘッジファンドをおすすめしないのはこんな人
自己運用したい人、取引が好きな人
四六時中、株のことを考えてしまう、自分で取引をしなければならない人はヘッジファンドは当然向いていません。
ヘッジファンドへ投資すると完全の任せになるので、一度投資すると取引をすることもなければ意見を言うこともありません。
長期前提の運用のヘッジファンドへ投資する場合は、それこそ10年単位で運用を任せたりするのが普通です。自己運用をしたい人はヘッジファンドそのものを検討しない気もします。
ただし、自己運用で成果を出すのは本当に難しく、筆者の体感では5年は真剣に相場と向き合い、相場のサイクルを一回り経験したところがスタートラインと言ってもよいくらいだと思います。
たまたま強気相場を投資開始時に引き当て、大きくリターンを出してしまっても相場サイクルの中(下落相場)で稼いだ資金を溶かしてしまうのが常です。
例えば、自己運用が好きでも5000万円ほどあるとして、4000万円はヘッジファンド、1000万円は自己運用といったやり方が良いと思います。
短期目線の人・派手なリターンが好きな人
ヘッジファンドに投資して半年、または1年でリターンを得たいという人はとても多いように思います。
しかし、短期でリターンを希望する時点で金融知識があまりにも浅いです。投資・運用とは時間を味方につけ、運用リターンを重ね、大きく資産を増やしていくものです。
短期で儲けようとするとそれはどうしてもギャンブルになってしまいます。
長期投資前提のヘッジファンドで運用するのであれば、最低でも5年、できれば10年スパンで運用の質を見極めたいところです。
運用は忍耐が必要で、あのウォーレン・バフェット氏の資産も実は95%が65歳以降に築いたものです。複利効果が加速していくことがよくわかりますね。
少額運用希望の方
100万円、200万円など少額運用したい方はヘッジファンドに向かないというより、ヘッジファンドへ投資できません。
日本国内のヘッジファンドに関しては1000万円程度が最低出資額となっています。これは私募ファンド故に募集人数が限られ、小口の資金を拾っていてはファンドの資産規模が大きくならず、運用に影響を与えてしまいます。(投資規模で上場企業にアクティビストとして提言するなどが不可能)
まずは、コツコツと、最低1000万円と生活防衛資金を確保した上でヘッジファンド投資を検討すると良いかと思います。
ヘッジファンドをおすすめできるのはこんな人
長期で複利効果を享受したい方
ヘッジファンドへの投資は長期目線が基本です。しかし、個人で長期で真剣に相場で運用していくのはあまりにも難易度が高いです。
安定運用のヘッジファンドであれば、一旦預けてしまえば毎四半期ごとのレポートなどで運用成績を確認するのみです。手数料はかかるものの、手間がかからないのはメリットが大きいです。
本業に本腰で取り組めますので、運用はやはりプロに任せるのが一番かと思います。
資産規模が大きい方
資産規模が大きくなると、個人でも運用が難しくなってきます。
1000万円以上の資金となると、運用すればリターンはその規模のおかげで大きくなりますが、リスクも比例して大きくなります。
相場の暴落に巻き込まれれば、1000万円が一瞬で700万円に溶けてしまったりしますからね。1億円であれば7000万円と3000万円減少したりもザラなのが相場です。
筆者は昔から株式相場はメジャーリーグのような場所なのに、素人投資家が参加できることに違和感を感じてきました。
そして素人投資家の資金が吸い込まれていくのを幾度と目にした時、やはり現役で結果を出しているプロに任せるのがベストであると思ったものです。
-

-
【2024年】日本国内のヘッジファンド14社をおすすめ順にランキング形式で一覧にして紹介!
資産運用の世界に足を踏み入れることは、多くの人が避けて通れない道です。特に、貯金が1000万円を超えた瞬間、その資産の増加の遅さに心を痛める方も少なくありません。 このような状況に直面した際、資産運用 ...
続きを見る
どのヘッジファンドを選ぶ?
ここからは筆者の意見になりますが、資産運用をするのであれば長期的な資産形成を目指し、不安のない老後を迎えたいものです。
そこでヘッジファンド選びという話になってきますが、やはり世界的に成功しているファンドを参考にするのが一番かと思います。
例えば、ジェームズシモンズのメダリオンファンドはドットコムバブルやリーマンショックを乗り越え31年間マイナス運用の年がありませんでした。
ウォーレンバフェット氏も、バークシャーハサウェイ運用開始後1965年から2014年まで50年でマイナスを出したのはわずか2回でした。
如何にマイナスを出さないことが長期複利運用で大切かがよくわかります。
今後ヘッジファンドを選ぶ際には、この「マイナスを出さないこと」に重点を置いているファンドを選ぶべきだと思います。
筆者ももれなく上記の哲学を実践しているヘッジファンド、BMキャピタルで運用しており、すでに10年近くが過ぎています。
BMキャピタルの特徴はバリュー株投資×アクティビスト戦略で相場の流れに関係なく、利回りを毎年コンスタントに積み上げていく手法をとっています。
同社については以下で詳しく述べていますのでぜひ参考にしてみてください。
>>> 和製国内ヘッジファンド・BMキャピタルの実態を徹底的に暴く。
ヘッジファンドをランキング形式でまとめている記事は以下になりますのでこちらも参考にしてください。