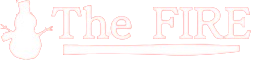パンデミックが流行した2020年3月以降、世界的に金融緩和が実施されました。その追い風を最もうけた産業がハイテク産業です。
パンデミックを期に大胆な社会変革が進み世の中のハイテク化が爆速で進行するなかでハイテク株は世界的に上昇していきました。
一番わかりやすい例はハイテク銘柄の比率が高い世界のハイテク先進国である米国のナスダック総合指数ですね。
ナスダックはコロナショックで6600ドルまで下げたあと、2021年末の最高値16200まで約2.5倍まで上昇していきました。
このような環境の中で満を辞して登場した投資信託に「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド」があります。
ゼロコンタクトの愛称で親しまれています。人間が相対することなく、今までと同様の生活を享受できる社会という意味が含蓄されていそうですね。
そんなゼロコンタクトですが、運用開始から半年ほどは調子がよかったのですが、その後下落基調が継続しています。
金融政策を理解している人であれば、容易に理解できる暴落ではあります。
本日は以下のポイントを中心にお伝えしていきたいと思います。
ポイント
- ゼロコンタクトはどのような特徴の投資信託なのか?
- なぜ直近ここまで下落しているのか?
- 今後の見通しはどうなのか?
- さらに魅力的な選択肢はあるのか?
関連)【ブログ随時更新】飛躍の2024年!今買いの一番儲かる投資信託銘柄はどれ?「安全」且つ「これから上がる」個人投資家が買うべき高利回りファンドを徹底調査!
ゼロコンタクトはどのような投資信託なのか?特徴は?
まず、ゼロコンタクトがどのような投資信託なのか見ていきたいと思います。
ゼロコンタクトの銘柄選択の特徴とは?
ゼロコンタクトは愛称の通り非接触型ビジネス関連企業の株式を中心に投資を行う投資信託となります。
わかりやすい例でいうとオンラインビデオ通話のZOOMなどが非接触型ビジネスの代表例ですね。
会議を顔を付き合わせる必要なくオンラインで行うビジネスが2020年以降大流行しました。まさに世相を反映したデジタル銘柄に投資をしていく投資信託ということになります。
あとで構成銘柄をみていきますが、米国をはじめとした外国銘柄を中心に投資をしています。そのため外貨建ての投資となるのですが、ゼロコンタクトは為替ヘッジは実行していません。
ARK社(アーク社)の助言を受けて銘柄選択を実行
ゼロコンタクトはアーク社の助言を受けて銘柄を選択しています。
日本では馴染みがないですが、米国では2020年に一斉を風靡した破壊的イノベーションファンド「ARKK」を運用しています。
ファンドマネージャーのキャシーウッドは2020年のハイテクグロース大相場のヒロインといっても過言ではない人物です。仕事ができそうなご尊顔をされていますね。

彼女が運用しているARKKですが、2020年に隆盛を誇りましたが、現在は見る影もありません。
今後の見通しの項目でも理由について触れるのですが、既にパンデミック前の水準まで基準価額が急落しています。

ARKKの基準価額の推移
ARKのようなETFを購入する場合、ボラティリティが高いことを許容する必要があります。
また一度暴落した場合、10年スパンで値を戻さない可能性も高く、かなり緊張感を持って毎日相場に向き合う必要があります。
基本的には、長期投資家であればARKKやゼロコンタクトのようなファンドを持つべきではありません。
どんな相場でも派手なリターンはなくとも着実なリターンをあげてくれるファンドに預けるなどするのが最適な戦略かと思います。
-

-
【ブログ随時更新】飛躍の2024年!今買いの一番儲かる投資信託銘柄はどれ?「安全」且つ「これから上がる」個人投資家が買うべき高利回りファンドを徹底調査!
パンデミックの影響が徐々に薄れ、我々はいま、ポストコロナの新たな時代に足を踏み入れています。特に注目すべきは、株式市場のダイナミックな変動です。 2020年の初旬に見られた株価の急落(コロナショック) ...
続きを見る
-

-
【2024年】日本国内のヘッジファンド14社をおすすめ順にランキング形式で一覧にして紹介!
資産運用の世界に足を踏み入れることは、多くの人が避けて通れない道です。特に、貯金が1000万円を超えた瞬間、その資産の増加の遅さに心を痛める方も少なくありません。 このような状況に直面した際、資産運用 ...
続きを見る
米国のハイテク企業を中心とした構成上位銘柄
現在2024年1月時点での構成上位銘柄は以下となります。
過去からの構成上位銘柄の推移は以下となります。
| 2024年1月末 | 2023年10月末 | 2023年7月末 | 2023年4月末 | 2022年10月末 | 2022年7月末 | 2022年5月末 | |
| 1 | COINBASE | COINBASE GLOBAL INC | COINBASE GLOBAL INC | SHOPIFY INC | ZOOM Video | ROKU INC | ZOOM VIDEO |
| 2 | ROKU | ROKU INC | ROKU INC | COINBASE GLOBAL INC | ROKU INC | ZOOM Video | ROKU INC |
| 3 | SHOPIFY | ZOOM VIDE | SHOPIFY INC | ROKU INC | SHOPIFY | BLOCK | COINBASE GLOBAL |
| 4 | BLOCK | ROBLOX CORP | BLOCK INC | BLOCK INC | ROBLOX CORP | UNITY | TWILIO INC |
| 5 | UNITY | SHOPIFY INC | UNITY SOFTWARE | DRAFTKINGS INC | TWILIO INC | SHOPIFY | BLOCK INC |
| 6 | ZOOM | DRAFTKINGS IN | DRAFTKINGS INC | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | COINBASE GLOBAL | TWILIO INC | SHOPIFY INC |
| 7 | DRAFTKING | BLOCK INC | ZOOM VIDE | ROBLOX CORP | BLOCK | COINBASE GLOBAL | SEA LTD-ADR |
| 8 | ROBLOX | UIPATH INC | ROBLOX CORP | UNITY SOFTWARE INC | DRAFTKING | ROBLOX CORP -CLASS A | UNITY SOFTWARE INC |
| 9 | UIPATH | UNITY SOFTWARE | UIPATH INC - CLASS A | UIPATH INC | UiPATH | DRAFTKING | UIPATH INC |
| 10 | TWILIO | TWILIO INC | TWILIO INC - A | TWILIO INC | NETFLIX | UiPATH | DRAFTKINGS INC |
上下動はありますが、銘柄の顔ぶれは殆ど変わっていませんね。
ゼロコンタクトの構成銘柄は助言を受けているARK社の旗艦ファンドであるARKKの保有銘柄と殆ど同じになっています。ちなみにARKKの構成上位銘柄は以下となります。
| 2024年1月末 | 2023年10月末 | 2023年7月末 | 2023年5月末 | 2022年10月末 | |
| 1 | コインベース | コインベース | テスラ | テスラ | イグザクトサイエンシズ |
| 2 | テスラ | ロク | ロク | ズーム | ズーム |
| 3 | ブロック | ユーアイパス | コインベース | ロク | テスラ |
| 4 | CRISPRセラピューティクス | テスラ | ズームビデオ | コインベースグローバル | ロク |
| 5 | ロク | ズームビデオ | ユーアイパス | ブロック | ブロック |
| 6 | ユーアイパス | ブロック | ブロック | イグザクトサイエンシズ | ユーアイパス |
| 7 | ズームビデオ | CRISPRセラピューティクス | イグザクトサイエンシズ | ユーアイパス | ショッピファイ |
| 8 | ロビンフッド | ロブロックス | ドラフトキングス | ショッピファイ | テラドック |
| 9 | ロブロックス | トゥイリオ | トゥイリオ | ドラフトキングス | コインベースグローバル |
| 10 | ユニティ | ユニティ | ユニティ | CRISPRセラピューティクス | CRISPRセラピューティクス |
ゼロコンタクトの構成首位のコインベースについてみていきましょう。コインベースは世界最大の暗号資産取引所です。

コインベースの株価推移
上場開始後から株価は下落の一途をたどっています。直近は少々回復していますが、まだまだFRBの利下げから遠い位置にある現状、今後も厳しいでしょう。
そんな銘柄がゼロコンタクトの首位銘柄なのです。しかも、ゼロコンタクトが投資している銘柄はショッピファイのような銘柄ばかりです。
結果として冒頭にお伝えしたような基準価額の推移となってしまっています。
ゼロコンタクトに関してはグロース株に投資しているようなものなので、限りなく個別銘柄投資に近いです。つまりはハイリスクハイリターンの投資ということです。
個別株投資に関しては、毎日相場を細かくチェックし、決算シーズンに業績を確認しその企業の成長性などを見極める必要があります。
ゼロコンタクトに決算の部分を委託しているようなイメージで投資をしていることになりますが、マクロ環境を完全に無視したテーマ投信です。
ずっとホールドすれば必ず大きな損を被る仕組みになっています。
本格的に投資をするわけでもないのに、こんなにハイリスクな投資をする必要はないのではと筆者は考え込んでしまいます。
もっと、堅実で、リスクの低い投資先は探せばいくらでもあるのです。
-

-
【ブログ随時更新】飛躍の2024年!今買いの一番儲かる投資信託銘柄はどれ?「安全」且つ「これから上がる」個人投資家が買うべき高利回りファンドを徹底調査!
パンデミックの影響が徐々に薄れ、我々はいま、ポストコロナの新たな時代に足を踏み入れています。特に注目すべきは、株式市場のダイナミックな変動です。 2020年の初旬に見られた株価の急落(コロナショック) ...
続きを見る
-

-
【2024年】日本国内のヘッジファンド14社をおすすめ順にランキング形式で一覧にして紹介!
資産運用の世界に足を踏み入れることは、多くの人が避けて通れない道です。特に、貯金が1000万円を超えた瞬間、その資産の増加の遅さに心を痛める方も少なくありません。 このような状況に直面した際、資産運用 ...
続きを見る
手数料はアクティブ投信の中では一般的な水準
手数料は以下の通りアクティブ投信の中では一般的な水準となります。
購入手数料:3.3%(税込)
信託手数料:年率1.7985%(税込)
手数料も重要ですが高いリターンをだしてくれる方が重要です。
それでは次の項目から重要なリターンに移っていきたいと思います。
投資信託「ゼロコンタクト」の運用実績を紐解く
では肝心の運用実績について見ていきましょう。
運用開始後半年は堅調だったが下落基調が継続
以下は基準価額の推移ですが、運用開始から半年で1.6倍までいきましたが、その後下落基調が続いています。
2024年2末時点では運用開始時点の半額で取引されているという状態になっています。大暴落ですね。しかしこれは必然です。理由については後でお伝えします。
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 29.71% | 21.06% | -5.64% | 34.74% | 99.64% |
| 2022年 | -24.11% | -35.90% | -6.24% | -15.60% | -61.50% |
| 2021年 | -0.24% | 13.03% | -13.20% | -15.23% | -17.03% |
ナスダック総合指数にも大きく劣後
ナスダック総合指数に組み入れられている銘柄を多く含んでいるのでナスダックと比較したものが以下となります。
ナスダックも2022年初頭より大きく下落していますが、ゼロコンタクトの下落の方が深刻ですね。
ARKKと殆ど同様の動きとなっている
ゼロコンタクトと最も近い動きをしているのがゼロコンタクトに助言を行っているアーク社が運用を行うARKKです。
実は先ほどの構成銘柄も殆どARKKと被っているので必然の結果ともいえます。2022年は▲70%というのは、なかなかインパクトがありますよね。
箸休め〜ゼロコンタクトの評判は如何に?掲示板で口コミチェック
掲示板を見に行くと、悲痛な叫びがかなり見受けられますが、ダメな投資信託を購入してはいけないと誓いたくなりますね。
もっとまともな投資先はたくさんあるはずなのですが、やはり難しいですね。
親戚の証券マンに聞いて見たが、1万まで戻らないと。最初からシナリオができていたのか。
高い勉強代になった。
-61.35%でもはやいつ売っても同じと思ってしまっているので逆に持ってますが
運用コスト考えたら馬鹿らしいのでしょうか。
同じ額運用するならもはや日本株に突っ込んで優待貰う方が幸せなのではと思っています
営業マンorウィメン?
絶対に勘違いしてはいけないのは、彼らは友達でもなけりゃ、当然だが身内でもない。
彼等は「ノルマのため売りたいだけ」。
キャバクラやガールズバーじゃないから、流石に色恋に騙されてる人はいないと想うが…。
キャシー・ウッド氏が活躍できる相場ではないですよね、今は景気拡大局面ではないので、グロース銘柄を触っては大怪我をします。
このゼロコンについけは、キャシーの責任は重大!悲しいですが、自己責任はありますけど。
ゼロコンタクトはコロナ拡散の中で生まれたファンドですが、今やコロナとは無関係になってしまった。再び浮上することは夢の又夢でしょうね。
えっ‼︎本当ですかぁ⁇そうですよねぇ😆 もぅ 買った時の3分の1になっちゃってるんです⤵️⤵️このままじゃやってられないですよね😤
詳しく、なぜゼロコンタクトが今の相場で下落を続けているのかを説きます。
なぜ2022年から運用実績が著しく低下したのか?理由を紐解く!
ゼロコンタクトの運用成績は残念ながら、お世辞にもよいものとは言えないと思います。
今後の見通しに移る前に、なぜ2021年後半から軟調に推移しているのか理由をみていきたいと思います。
2022年からの下落は金融引き締め懸念に長期金利の上昇が要因
そもそも2020年からハイテク株が上昇した要因は以下の2点です。
- 社会変革によるデジタル化が加速するという思惑
- 米国の大規模な金融緩和による長期金利の低下
1点目に関しては確かにデジタル化は加速してハイテク企業の利益は急上昇しました。しかし、2021年の後半になると成長に陰りが見えて、2022年の成長率が低下する観測がでてきました。
グロース企業の株価は1年から2年先を見越して値付けされます。
2022年の成長率低下が見込まれる段階では株価は逆流を始めていくのです。
2点目の金融緩和についても考えてみましょう。
パンデミックを受けて米国をはじめ世界の中央銀行は企業の破綻と国民の生活を救うために大規模な金融緩和を実施しました。
結果として長期金利が低下していきました。以下は米国の10年債金利の推移です。

ちなみに2023年12月時点では、10年債はさらに上昇しています。

米国10年債の利回りは2022年以降急激に上昇
金利の低下を受けてグロース株を中心に強烈な追い風が吹きました。(次の項目で説明します)
しかし、2021年後半以降インフレ率が急上昇したことによって、金融引き締めを行う必要性がでてきました。
実際に米国が金利を引き上げているのは2022年に入ってからです。
しかし、株価は1年から2年先を見通して動くので上昇してきたグロース株を中心に売り込まれていきました。2024年1月の今も引き締めは続いています。
なぜ金利が低下するとグロース株(成長株)が大きく上昇するのか?
なぜ、長期金利が上昇するとグロース株の株価が下がり、長期金利が下落するとグロース株の株価が上昇するのか疑問に思われた方も多いでしょう。
詳しく説明すると長くなりますので、簡単にイメージだけでもお伝えしていきたいと思います。
グロース株は将来の成長した後の利益に期待して投資家が購入します。ここで重要なのが将来の利益を現在時点でどのように見積もるのかという点です。
経済学では現在の1万ドルと10年後の1万ドルの価値は異なります。
なぜなら1万ドルを運用すれば10年後には1万ドル以上にすることが可能だからです。利回り3%の米国債に投資するだけで10年後には1万ドルが1万3400ドルになっていますからね。
ということは将来の利益も現在の価値に置き直す必要があるのです。
将来の利益を現在時点の価値に置き直す割引率の算定は複雑なのですが、間違いなく言えることは国債の金利が割引率の式に入っているということです。
つまり、将来の利益を割り引くための長期金利が上昇すれば将来の利益の現在の価値は低下することになります。

つまり、将来の利益見通しが変わらなかったとしても、長期金利が上昇することでグロース株の企業価値は小さくなってしまうのです。
逆に長期金利が低下することで将来の利益の現在時点での価値が上昇するので企業価値は大きくなります。
ざっくりいうと上記のような理由で長期金利の水準がグロース株の株価に影響を及ぼします。
今後はどうなる?見通しが暗い理由とは?
さて重要なのは今後です。先ほど挙げた2点の懸念が今後も払拭されないのかという観点から考察していきます。
ハイテク企業は2020年から2021年に今後数年の成長を先取りしてしまっている
2020年から2021年の社会変革は早すぎてゼロコンタクトの保有銘柄の多くは今後数年の成長を先取りしてしまっています。
例えば長らくポートフォリオに入っているROKUの今後の成長予測をみてみましょう。
2023年(Current Year)は312.3%のマイナス成長が予測されています。来年2024年も11.8%のマイナス成長と低迷が予想されています。2023年のマイナス成長をさらにマイナス成長するのです。
ROKUは2020年から2021年にかけては年率200%以上の高成長を実現してきました。完全に成長を先取りした結果、現在は成長の足踏みをしてしまっているのです。
また、後述しますが高金利とインフレが継続したことで今後は景気後退が見込まれ企業の業績が悪化していくことが見込まれています。
高成長を前提として高いバリュエーションで取引されていたのですが、成長率が低下すれば最早グロース株ではありません。
結果として株価は大きく下落していっています。

ROKUの株価の推移
今後革新的な変革が起こり成長予測が跳ね上がらない限り、しばらくは低い水準で停滞することが予想されています。
そして、構成上位銘柄はこのような企業が多くなっています。安易に既に割安であると考えてはいけません。ITバブル崩壊した2000年から2002年にはナスダックは90%下落したのですから。
下落耐性が強い、長期運用に適した投資先を選びましょう。
-

-
【ブログ随時更新】飛躍の2024年!今買いの一番儲かる投資信託銘柄はどれ?「安全」且つ「これから上がる」個人投資家が買うべき高利回りファンドを徹底調査!
パンデミックの影響が徐々に薄れ、我々はいま、ポストコロナの新たな時代に足を踏み入れています。特に注目すべきは、株式市場のダイナミックな変動です。 2020年の初旬に見られた株価の急落(コロナショック) ...
続きを見る
インフレはおさまる気配を見せず金利は高止まりを続けることが見込まれる
基準価額下落の2つ目の要因として挙げたインフレ率も高騰の一途を辿っています。2023年になってようやく年率3%まで下落して少し落ち着きつつあります。
前年同月比で3%という水準は米国中央銀行のFRBが目指す2%に近づいてきています。
しかし、米国の10年債金利は昨年の高値を伺う動きを見せています。

米10年債金利の推移
これは債券投資家がインフレ第二波が発生することを織り込んでいることを意味しています。
現在、インフレ率がさがったように見えているのはエネルギー価格のような変動率が高いものが下落した影響を受けています。
しかし、賃金や家賃などの粘着性のあるインフレ率は下落しておらず高止まりしています。以下からわかる通り粘着性のある項目のインフレは全くおさまっていません。

直近、エネルギー価格は反発してきておりインフレ2波の到来する確率が高くなってきているのです。歴史は繰り返すといいますが、1970年代もインフレが3回にわたって発生しました。

今回も長期間インフレと、それに伴う高金利にさいなまされることが想定されます。
相場環境によらずリターンが狙える投資先への投資が推奨されます。
-

-
【2024年】日本国内のヘッジファンド14社をおすすめ順にランキング形式で一覧にして紹介!
資産運用の世界に足を踏み入れることは、多くの人が避けて通れない道です。特に、貯金が1000万円を超えた瞬間、その資産の増加の遅さに心を痛める方も少なくありません。 このような状況に直面した際、資産運用 ...
続きを見る
インフレ1波と2波の間に不況(=リセッション)が訪れる
インフレ2波到来のまえに一旦、訪れるのが不況です。インフレで米国人の財布は枯渇しており、金利上昇でローンの支払いなどで家計が更に圧迫しています。
むしろ、不況が到来することでインフレは沈静化していきます。不況がおとずれると当然企業の収益も激減していきます。

企業の株価は「EPS(=1株あたり純利益) × PER (人々の熱狂の度合い)」で算出されます。EPSが大きく下落し、人々の気分が落ち込む状況では株価は当然大きく下落していきます。
不況が訪れるとFRBは一転して利下げを行い景気を引き上げようとしますが、それが最後の暴落の合図です。
以下のとおり過去50年の調査で金利を引き下げたあとに株価は大きく暴落していることがわかります。

また不況になるとドル円も急落していきます。現在の150円のドル円レートは日米の金利差を背景に上昇してきているからです。

FRBが金利を引き下げると日米金利差は縮小し、ドル円は急激に円高に振れていきます。すると円建でみるとゼロコンタクトの基準価格も更に暴落していくことが想定できるのです。
そして、また金融緩和をおこなうことによりインフレ再燃が本格化していくというイタチゲームを繰り返すことになっていきます。
まとめと魅力的な選択肢とは?
ゼロコンタクトについてまとめると以下となります。
ポイント
- アーク社の助言を受けて主に米国のハイテク企業に投資
- 2021年の前半まではリターンはよかったが、そこから基準価額は運用開始時の半分に下落
- ナスダック総合指数にも大幅にアンダーパフォームしておりARKKと同様の動き
- ハイテクグロース企業は利益成長見通しが低下しており、金利も高止まりが見込まれることから今後も軟調となることが想定される
- 更にリセッションによる利益の減少と円高で大きな打撃を2024年に被る可能性が高い
そもそも、なぜ投資をするかというと資産を安定的に増やしたいからではないでしょうか?
筆者が目指す資産運用はヘッジファンドの帝王レイダリオが運用するブリッジウォーターアソシエイツのような綺麗な右肩上がりのチャートです。
→ 世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーターアソシエイツを解説。帝王レイ・ダリオの投資哲学とは?

ブリッジウォーターは最低出資金額が1000億円以上なので個人には投資できません。
しかし、ブリッジウォーターと同じ哲学で運用を行い、まさに上記と同等または更に優れた右肩上がりの運用を行っているファンドは存在します。
例えば、筆者が運用を長期的に任せているBMキャピタルなどはまさにセクターローテーションのボラティリティの影響も受けず、堅実なリターンをもたらしてくれています。