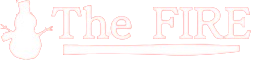2010年代は新興国にとって苦境の10年間でした。株価は低迷しましたが確実に経済成長を実現し世界経済に占める比率は既に6割となってきています。にも関わらず時価総額は世界全体の1割強と過小評価されています。

2020年からの10年間は遅れを取り戻すような動きを見せることが想定されます。そして、その中で最も期待されるのが新興国の雄である中国です。中国は、あのヘッジファンドの帝王、レイダリオ氏が米国の次に世界の覇権を取る国としています。
そして、世界一のヘッジファンドであるブリッジウォーター社も中国における運用資産が倍増しています。
[香港/上海 10日 ロイター] - 米ヘッジファンド運用会社ブリッジウォーターが中国の運用資産を過去1年間で200億元(29億3000万ドル)に倍増させたことが、関係筋の話や公式データで明らかになった。中国で最大の外資系ヘッジファンドとしての地位を盤石にしつつある。
同社最初の中国ファンドは、2018年10月の設立後の4年間で、年率15.6%のリターンを達成。21年12月に立ち上げた別のファンドは、22年12月までの期間で8.4%の純リターンを実現したと、関係筋は語った。中国の主要株価指数であるCSI300指数は昨年、20%余り下げた。
中国は高い成長率を誇るにも関わらず、株価が著しく割安に評価されてきました。長期的にみると株価は適正な価格に修正されます。2023年以降は更に金融緩和を行なっているのも大きな追い風となっています。
実際、2023年7月の最新データでブリッジウォーターに限らず海外のヘッジファンドも中国株に殺到しているというデータが示されています。

中国は米国と比するレベルでテクノロジーが進展してきており、まさに今本格的に飛翔の時を迎えようとしています。
今回は今後も株式市場の上昇が期待できる中国市場に先駆けて投資を行い、すでにアクティブリターンを叩き出している国内ヘッジファンド「オリエントマネジメント」について紹介していきたいと思います。
中国相場は今が正念場ですが、そんな中でも高い利回りを出していることから、中国当局も株価引き上げにテコ入れを行っていますし、今後相場が上向きになった時にどうなってしまうのでしょうか?
| オリエントマネジメント | 上海総合指数 | 香港ハンセン指数 | |
| 2021年6〜12月 | +10.84% | +13.34% | -19.09% |
| 2022年通年 | +5.70% | -15.12% | -15.45% |
| 2023年1〜6月 | +16.91% | +3.64% | -4.37% |
| 合計 | +36.96% | -10.84% | -34.50% |
オリエント・マネジメントの特徴
- 総合:
攻めに特化した新興国投資を行うヘッジファンド。新興国の中でも今後大きなリターンが見込める中国の株式に投資を行う。
- 下落耐性:
新興国投資なので当然リスクは高いが、綿密なファンダメンタルズ分析により割安な銘柄に投資していることと、既に中国の株式市場がかなり割安で推移しているので下落余地は少ないことが見込まれる。
- 運用手法:
高い成長性と割安度でバランスをとったポートフォリオを組成し堅実な運用手法を採用している。
- ファンドマネジャー:
以前にも新興国ファンドを運用、バブルに乗りハイリターンを獲得した過去があり、詳細は担当者に聞くとよい。
経済成長率に対して明らかに割安に評価されている
まず、中国株は特に割安に放置されているという点が挙げられます。以下は日経平均と上海総合指数の値動きです。
経済成長率は以下の通り殆ど0%成長の日本に比べて、徐々に安定してきているとはいえコロナショックを除けば中国は6%以上の高成長を維持しています。
むしろ、コロナショックで混迷を極めた2020年でもプラス成長をしているのは脅威的ですね。安定性が高い傾向があります。

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 中国 | 8.5 | 8.3 | 9.1 | 10.0 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14.2 | 9.6 | 9.4 | 10.6 | 9.6 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.0 | 2.2 | 8.5 | 3.0 | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.4 |
| 日本 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | -1.2 | -5.7 | 4.1 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | -0.4 | -4.3 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 米国 | 4.1 | 1.0 | 1.7 | 2.8 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 0.1 | -2.6 | 2.7 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | -2.8 | 5.9 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
明らかに中国株は実力に比して過少評価されているのがわかります。日本よりは成長している米国と比べても高成長を実現しているにも関わらず、米国のS&P500指数に大幅に劣後しています。
株式市場は短期的には過少評価されることはありますが、長期的には適正価値に収斂していきます。このアンダーバリューが解消するだけでも中国株には大きなチャンスが転がっているのです。
実際、割安指標として広く活用されているPERで、中国は他の国と比較して非常に低い状態となっていっます。

中国の下にあるインドのPERは30倍を超える割高水準となっています。インドはわかりやすい成長国ですから、明らかに割高ですね。わかりやすいものほど早く高くなります。

中国H株とは中国本土で登記をおこなっているものの香港取引所に上場している企業の株のことを指します。ハンセン指数の構成銘柄として選ばれている銘柄もあります。
中国の株式市場については以下が詳しくまとまっていますのでご覧ください。

コラム:拡大しつづける中国の株式市場
中国の証券市場は近年急速に拡大しています。2020年末時点で7兆ドルにせまる水準に伸びています。

新興国の中では圧倒的ですね。更に、長らく世界第2位の証券市場であった東京証券取引所に並ぶ水準にまで急拡大しています。上海と香港を加えると既に東京証券取引所を上回るレベルになっています。

しかし、既に中国は日本の3倍のGDPを有する超大国になっています。経済規模から考えると今後さらに伸びていくことが容易に想像できますね。
中国は米国に次いでイノベーションが起きている!
この項目は中国の発展についてお伝えしたコラム的なものなので、あまり興味のない方は次の項目にジャンプしてください。
中国といえば新興国、遅れているイメージを未だに持っている方もいらっしゃると思いますが、それは認識を改める必要があります。
筆者自身中国を侮っていたのですが、昨年深圳を訪れた時驚愕しました。街中でドローンが飛んでいますし、まるで夜はプロジェクションマッピングのように鮮やかで近未来にきている印象をうけました。

では実際に中国がどれほどテクノロジー国家に成長しているかを見てきましょう。
BATHはGAFAMに対抗しうる巨大企業となっている
米国の巨大ハイテク企業としてGAFAMが現在世界を席巻しています。
G:Google
A:Apple
F:Facebook
A:Amazon
M:Microsoft
一方、中国にも巨大なBATHという企業群が存在しています。
B:Baidu(百度)
A:Alibaba
T:Tencent
H:Huawei
それぞれのデータを比較したものが以下となります。
| 2023年3月時点 | 売上 (百万ドル) |
純利益 (百万ドル) |
時価総額 (百万ドル) |
PER |
| 182,527 | 40,269 | 1,391,882 | 35.7 | |
| Apple | 274,515 | 67,091 | 2,048,457 | 33.6 |
| 85,965 | 29,146 | 808,112 | 28.1 | |
| Amazon | 386,064 | 21,331 | 1,552,692 | 75.0 |
| Microsoft | 143,015 | 44,281 | 1,753,113 | 35.3 |
| Baidu | 16,472 | 3,457 | 90,589 | 26.8 |
| Alibaba | 78,417 | 22,989 | 646,468 | 26.4 |
| Tencent | 58,044 | 14,355 | 791,110 | 41.6 |
| Huawei | 132,123 | 9,646 | 169,230 | 17.5 |
まだまだGAFAMには追いつけてはいませんが、売上高や利益の成長率はBATHが圧倒しています。いつかGAFAMに比肩するレベルに成長していくと考えています。
電気自動車(EV)やドローンでも米国に対抗
持続可能な世界を目指すSDGsの進展によって2020年移行電気自動車に注目が集まっています。米国企業のテスラがトヨタの時価総額を抜き自動車産業でトップになったことが注目を集めました。
クリーンエネルギーの熱は中国でも湧き起こりました。中国は実はEV先進国でNIOを筆頭として2020年に株価は急騰しました。

中国の電気自動車(EV)メーカーの時価総額が急拡大している。国家を挙げたグリーンエネルギー目標に加え、米EVメーカーの テスラ の驚異的な株価急騰の再現を期待する個人投資家の存在が背景にある。
ファクトセットによると、EV専門メーカーの蔚来汽車(NIO)の米国預託証券(ADR)は今年に入り約11倍に跳ね上がり、16日時点で時価総額は700億ドル(約7兆2200億円)弱に達している。香港では著名投資家ウォーレン・バフェット氏が出資する電池・自動車メーカー、比亜迪(BYD)が4倍余りに上昇し、時価総額は690億ドルとなっている。
各社はこうした急騰によって、 ゼネラル・モーターズ (GM)や フォード・モーター など従来型の自動車大手と肩を並べるまでになった。GMの時価総額は590億ドル、フォードは360億ドルだ。
またドローンの分野でも中国は世界を凌駕しています。特に深圳からスタートしたDJI社は現在ではドローンの世界シェアの約70%を占める巨大企業に発展しています。
そのほかにもEHANGやYuneecなどドローン会社が次々と興り世界市場を席巻しています。
最先端のテクノロジーを先取りしている中国は最早技術大国というレベルにのし上がっているのです。
更に最近は5G分野で覇権を握るべく投資金額を増加させています。
積極的に政府がベンチャー投資を行いユニコーン企業を続々輩出
なぜ、中国が技術大国にのし上がってきているかというと国が積極的に新しい産業に投資していることが主因です。
以下は日本と中国のベンチャー投資実行額の推移です。中国は日本の17倍の額のベンチャー投資を実行しています。
結果として、中国では米国についで多くのユニコーン企業を輩出しています。
ユニコーン企業とは?
- 創業から10年以内
- 評価額10億ドル以上
- 未上場
- テクノロジー企業

残念ながら日本はランクインすらしていませんね。新興産業が起こりにくい環境となってしまっているのです。
今まさに中国株が飛翔する刻と考える理由
新興国には株価が高騰する水準が存在します。例えば日本の日経平均株価の値動きをご覧ください。

株価が本格的に急上昇しているのは1980年代に入ってからです。当時の日本の1人あたりGDPの水準は10,000ドルという水準でした。
一人当たりGDPとは言い換えると所得水準です。所得が1万ドルつまり100万円未満の国では生活するのに必死です。つまり、国民が株式投資をする余裕なんてありません。
しかし1万ドルを超えると所得の伸びが加速し、自国民が投資をする余裕が出てくるのです。すると、ここがチャンスとばかりに株価が暴騰する環境が整うのです。
そして、今まさに中国が1人あたりGDP1万ドルの水準を超えるフェーズに差し掛かっているのです。

今まで低迷していた株価の再評価が行われる素地が整い、今まさに中国株が本格的な上昇をしていく環境が整ったといえるでしょう。
そして特筆すべきは中国が金融緩和を始めたことです。
アベノミクスで株価が大きく上昇したことは記憶に新しいですが、その株価上昇の原動力になったのは日銀による金融緩和です。
パンデミックで米国株が急騰したのも大規模緩和を実施したからにほかなりません。
2023年7月現在、中国は世界に先駆けていち早く金融緩和を実施し金利を引き下げています。
投資マネーというのは魅力的な投資対象に加速度的に集まっていきます。2022年からは相対性から注目を集めて中国に世界の投資マネーが流入していくことが想定されています。
早いうちにこの波に乗った方が高いリターンを見込むことができます。
超有望中国株ファンド「オリエントマネジメント」とは?
筆者はオリエント・マネジメントというヘッジファンドを通じて運用を行なっています。筆者は中国株について個別株の分析をするのは非常に難しいと考えています。
なぜなら自分が日本にいるため、どのサービスが魅力的なのかという一番大切なことを体感することができないためです。
やはり、個別株投資は現地にいることが一番の強みとなります。
例えば、日本で「かつや」が美味しいと話題になり、運営する「アークランドサービス」が10倍になったことは有名な話です。

もし、米国や中国に在住していたら決して投資することなんてできないですよね。やはり現地に実際に触れていないと本当に魅力的な銘柄というのは見つけられないのです。
日本の中国株を運用している投資信託もファンドマネージャーは日本にいます。そのため、本当に旬の中国株に投資できているかは疑問です。
筆者が中国株に投資する先として選択しているのがオリエントマネジメントです。オリエントマネジメントはファンドマネージャーは香港とシンガポールに拠点を置き現地の情報を収集しています。
シンガポールは華僑が多く存在しており、中国の富裕層からの話もきけるネットワークが発展している場所ですし、香港は言わずと知れた中国の中心的な金融センターです。
オリエントマネジメントのファンドマネージャーは日本株や新興国株で10年程度の実績があり、合計100億円以上の資産を運用している実績があります。
今後、伸びる可能性が高い中国株に効果的に投資する先として最も有効な選択肢だと考え投資を実行しています。
コラム:中国の民間企業には多大な投資機会が広がっている
一言に中国企業といっても国有企業と民間企業があります。以下は国有企業と民間企業の株価の比較です。
青:民間企業
黒:国有企業
国有企業は生産性の向上が非効率で株価が上昇していませんが、民間企業の株価は上昇しています。
現在は一時的に凹んでいますが、逆をいうと割安に仕込む好機が訪れているとみることができるのです。
中国の民間企業には多大な投資機会が広がっているとみることができるでしょう。では中国株でリターンを得るための魅力的な選択肢についてお伝えしていきたいと思います。
オリエントマネジメントは中国株が暴落する局面でも年率25%のリターンを出している
実際に筆者が預けてから3ヶ月でオリエント・マネジメントは大きな成果を出してくれています。中国株は2021年は後半政府によるIT企業の締め付けが痛手となり大きく下落してしまいました。
香港ハンセン指数は一時50%下落しました。(香港ハンセン指数はリーマンショック級を食らっています)しかし、オリエントマネジメントはこのような苦しい環境の中でも5.8%のリターンを出してくれていました。下落相場は最もファンドマネジャーの手腕が試されるタイミングです。

2022年も後半に入り金融緩和も実施され株価に対して大きな追い風が吹いていましたが、2023年後半までは横ばいが続いています。なんなら下落しており、中国当局が本腰で株価引き上げ政策に乗り出しています。


この相場で、オリエントマネジメントは上半期で約+17%のリターンを叩き出しており、市場を完全にアウトパフォームしています。
厳しい環境でもリターンが出せるファンドが、追い風が吹いていればどれだけのリターンを狙えるかは想像するとワクワクしますね。
先述したように今中国株には大きな追い風が吹いています。アベノミクスも2012年から2015年に大きく株価が上昇しました。政府が株価に対してテコ入れを始めることが投資家には好機なのです。筆者はアベノミクスで億り人に成り上がった人を何人も見てきました。

中国当局が、国内株式取引の印紙税を最大50%引き下げる案を取りまとめたことが複数の関係者の話で分かった。早ければきょうにも発表される可能性があるという。
低迷する株式市場のテコ入れが狙い。
中国、株式市場テコ入れへ印紙税引き下げ案 最大50%=関係筋
中国が株価対策を相次いで打ち出している。株式取引に必要な印紙税の税率引き下げ、新規株式公開(IPO)の段階的抑制、上場企業の大株主による自社株売却の制限などだ。
相場に乗ってさえいれば、大きなリターンを確保できたのです。この追い風が吹き始めた最初の局面で投資をして大きなリターンを狙っていきましょう。
詳しい内容については以下の公式ページから問い合わせて直接聞いてみましょう!
ここで重要なことなのであえて言いたいと思います。周りで裕福になった目上の方々の中には以下の方が一定数存在しているのではないでしょうか?
- ITバブル崩壊後にIT企業を購入した
- リーマンショックで大金をつぎ込んだ
そうです。株式市場が暴落している時に資金を突っ込むことで大金を手にすることが可能なのです。日本や米国ではこのような暴落が起きていませんが、中国では今まさにリーマンショック級の暴落に見舞われているのです。
そして重要なことに中国経済は成長を続け、中国企業のEPSも増加しているにも関わらずです。
正直いって、これは垂涎物のチャンスであると筆者は考えてオリエントマネジメントに投資をしています。
「虎穴にいらずんば虎児を得ず」という諺の通り、こういうビッグチャンスに投資をするのが合理的なのです。リスクは取るべき時に取るものであると確信しています。
ボラティリティが高いので、全財産を投じるのはおすすめしませんが、最低出資額の1000万円程度であれば、十分にポートフォリオの活性化に繋がる可能性があります。
配当利回り10%超えの企業に投資!?オリエントマネジメントの投資事例を紹介!
オリエントマネジメントが実際にどのような銘柄に投資をしているのかもお伝えしていきたいと思います。
神華能源 (上海A 501088、香港 1088)

神華能源は石炭の生産、販売、輸送、発電を手がける総合エネルギー会社で、内モンゴル等に炭鉱を保有し石炭生産量は世界最大規模の企業です。
投資を実行した時点の株式情報は以下となります。
| 時価総額 | 約6億6000億円 |
| 株価(上海A市場) | CNY 19.58 |
| 株価(香港市場) | CNY 13.55 |
| PER(H株) | 7.2倍 |
| PBR(H株) | 0.9倍 |
| 配当利回り(H株) | 13.1% |
中国の銘柄の中には上海市場(A株)と香港市場(H株)に二重上場している銘柄が数多くあります。神華能源もその一つです。
香港市場に上場されている分が、上海市場に比べて40%ほど割安なので香港市場に上場しているH株に投資したとしています。
そして注目すべきは割安指標ですね。PER7倍はかなり割安ですし、特筆すべきは配当利回りが13%ということです。
配当利回りが高いと株価が下落すると更に配当利回りが高くなるので買いが入りやすくなります。
つまり、下落する可能性を抑えられるのです。オリエントマネジメントは以下のポイントで投資を行い、株価値上がり益と配当益を二重で獲得しています。
新華文軒 (上海A 601811、香港 0811)
教科書や教材などを販売する流通事業と書籍・定期刊行物の出版事業が柱。音楽・映像作品やデジタル出版物も発行している企業です。
投資を実行した時点の株式情報は以下となります。
| 時価総額 | 1199億円 |
| 株価(上海A市場) | CNY 8.42 |
| 株価(香港市場) | CNY 4.73 |
| PER(H株) | 5.7倍 |
| PBR(H株) | 0.7倍 |
| 配当利回り(H株) | 6.5% |
A株とH株に1.8倍の差があったのでH株に投資をしたとしています。PERは5.7倍、PBRは0.7倍と著しく割安ですね。
投資した時からの株価推移は以下です。6.5%の配当金と株価値上がり益の両方が取れています。
まとめ
今回のポイントは以下となります。
- 中国の株価はアンダーバリューされている
- 今後まさに株価があがる水準になっている
- 既に米国につぐハイテク大国になっている
- 現地に根ざした情報を得られることが重要
- 拠点が中華圏にあり十分な実績を備えたファンドマネージャーによって運用されるオリエントマネジメントが魅力的
- 2023年中盤で千載一遇のチャンスが訪れている
- 高配当かつ割安な銘柄の適切な時期に渡欧しを行いアクティブリターンを作っている
↓↓↓↓
オリエント・マネジメント公式ページ