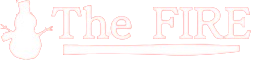ファンドラップは2015年以降くらいから多くの人が活用し出したように感じます。
ネット証券の登場で、証券会社も株売買などの手数料の商売の雲行きが怪しくなったため、ファンドラップに軸足を移したとの話を筆者も証券会社に務める友人より聞いたことがあります。
実際に、どこの金融機関も退職金などを受け取った投資家などに積極的にアプローチしているように思います。
これまでに複数のファンドラップを調べてきましたが、今回はみずほ証券のファンドラップについて調査していきたいと思います。
- ファンドラップはひどい!?儲かった人は少なく大損した人が多いと評判の金融商品を野村証券のラップ口座を例に紐解く!おすすめできるのか?
- 三井住友銀行が提供する評判のSMBCファンドラップを手数料や運用実績を含めて徹底評価!
- みずほ証券のファンドラップの実績は?評判は良いのか?Mizuho Fund Wrapとファーストステップの2商品を比較
- 三菱UFJ信託銀行が提供するMUFGファンドラップはひどい?評判の悪い理由を運用実績や手数料を踏まえて紐解く。
- 【ひどい?!】りそなファンドラップで運用するデメリットは?解約したい人続出?運用状況などから徹底考察!
- 評判の日興ファンドラップを運用実績や手数料を含めてわかりやすく評価!
ファンドラップとは?
ファンドラップとは、以下の図に集約します。

投資家が証券会社などと投資一任契約を結び、証券会社が投資家の代わりに株式市場や債券市場などで運用を行います。
これがファンドラップのサービスの概要です。要するに、投資家は何も考えず金融機関に運用を全部やってもらえるということですね。
ちなみに、単純に投資家が投資信託を購入するのとどう違うのかというと、ファンドラップの場合は投資家が堅実運用を願うのであれば堅実運用を行い、積極運用を願うのであればリスクを取ります。
投資信託は一つの利回りしか存在しません。しかしファンドラップの場合は投資家ごとに投資方法が変わってきますので、「ファンドラップはリターンが良いのか?」と聞かれても「人による」と言う回答しかできないのです。
つまり、基準がないのでファンドラップは本当に投資家に利益を提供しているのか疑問視した金融庁が、その運用実態の透明性を課題としています。
- ファンドラップ・バランス型ファンド ファンドラップの最低契約金額が低くなり小口化していく中で、顧客にとってファンドラップの投資一任運 用に係る報酬とサービスの対価関係が不明確であり、その点についての説明が十分になされていない。
- ファンドラップ・バランス型ファンドと共に、他の複数の商品を併せて保有する顧客の中には、ポートフォ リオにおける両者の位置付けを不明確なまま組み込み、全体の最適化を図れていない例がある。
全国銀行協会は115行を対象に仕組み債やファンドラップなど運用商品をめぐる実態調査に乗り出す。日本証券業協会も仕組み債のリスクを正確に伝えるよう指針を改める。不安定な市場動向が続けば、損失を抱える顧客が増えかねない。金融庁も販売体制を検証する方針だ。政府の資産所得倍増プランの実現性を高めるためにも販売体制の構築が重要になる。
みずほ証券が提供するファンドラップとはどのような商品?
ファーストステップとMizuho Fund Wrapと2つの商品を展開
以下の通り2つの商品を展開しています。住み分けとしては、ファーストステップは安全運用の初心者向け、Mizuho Fund Wrapはアクティブ投信(ファンドが指数を上回るパフォーマンスを狙う)運用であるため、プロ向けとなるでしょうか。
(そもそもプロはファンドラップで運用しないかもしれませんが)
| 商品①ファーストステップ(伝統的な投資スタイル) | 商品②Mizuho Fund Wrap | ||
| ご契約金額 | 500万円から | 1,000万円から | |
| 特徴 | 対象資産の期待リターンとリスク、資産間の相関係数の推計等を通じ、最適な資産配分による運用を行います。 | アクティブ運用で世界屈指の規模と歴史を誇るCapital Groupの投資哲学に基づいた資産運用をご提供します。 | |
| 長期的な視点に立つ国際分散投資を基本としつつ、短・中期の経済見通しや市場分析等を総合的に勘案し、資産配分を決定することで、リターンの獲得を目指します。 | 各国の経済情勢や企業業績等、運用環境の分析をふまえ、ファンダメンタルズ調査に基づいたアクティブファンドを組み合わせてリターンの獲得を目指します。 | ||
| 投資対象ファンド※1 | インデックスファンド アクティブファンド | アクティブファンド | |
| 報酬(手数料)(税込み・年率) | 投資一任契約に係る報酬 | 【固定報酬型のみ】最大1.650% | 【固定報酬型のみ】最大0.880% |
| 信託報酬の目安※2 | 0.18%~0.33%程度 | 0.50%~0.69%程度 | |
| オプション契約 | ─ | ─ | |
| 付帯サービス | 相続時受取人指定特約※3 | 相続時受取人指定特約※3 | |
最低契約額は?
ファーストステップが500万円〜、Mizuho Fund Wrapは1000万円からとなっています。
Mizuho Fund Wrapの方が敷居が高くなっています。上記2つなら筆者であればファーストステップにしますし、1000万円以上契約する予定でもファーストステップにすると思います。
そもそもインデックスに勝つとはとても難しいものです。Mizuho Fund Wraphはアクティブ投信のみを購入して運用するとのことで、散々投信を分析してきた筆者にとっては非常に恐怖があります。
ファーストステップの分配は以下の通り8つの投資信託で堅実運用を狙います。

テーマ投信などを買われて2022年のような相場を迎えたら資産が吹っ飛んでしまいます。
手数料は?
ファーストステップが最大1.650%+0.18%~0.33%程度となっています。2%には収まりそうですね。
Mizuho Fund Wrapは最大0.880%+0.50%~0.69%程度となっています。1.5%程度でしょうか。他ファンドラップに比べると良心的です。
投資方針のバラエティ
こちらは他ファンドラップとほぼ同様で、5つの方針から選べます。以下はファーストステップの選択肢ですが、安定型がいいと思います。
Mizuho Fund Wrapは以下の通りとなります。Aggressive Growthとか、どんなリターンを出しているのか見てみたいものです。

みずほファンドラップの運用実績、利回りは?
上記で述べたように、当然ですが明確なリターンは分かりません。
一人一人、運用方針が異なり、ファンドラップの利回りは◯%と明確に言えない商品だからです。そして金融庁は実態を確認すべく、ファンドラップを提供している各金融機関に成績の提出を命じました。
以下が結果です。どのプランの、どの投資方針によるものかは分かりません。
| 商品名 | 過去3年 | 過去5年 |
| みずほファンドラップ | 5.76 | 3.18 |
| ダイワファンドラッププレミアム | 8.09 | 5.99 |
| 野村SMA | 7.6 | 3.99 |
| 野村ファンドラップ | 7.84 | 4.26 |
| ダイワファンドラップ | 8.23 | 4.74 |
| 日興ファンドラップ | 7.7 | 4.11 |
| SMBCファンドラップ | 6.73 | 4.11 |
いずれにせよ、みずほファンドラップが提出した数字はベストなものである可能性が高く、それも5年で平均3%程度のリターンなので、あまり投資妙味はないですね。
一番良いダイワファンドラッププレミアムでさえ6%程度なので、インデックスファンドを購入していた方がまだマシなのではないかという水準です。2020年はバブルでしたし、かなり控えめな成績です。
口コミ評判
以下はインターネット上で見られた評判です。
みずほ証券が75歳以上の人を対象にファンドラップ購入手数料をキャッシュバックだってさ。
75歳で投資始めない方がいいと思うんですけど。 pic.twitter.com/eI38auYxyL— ふまつげん (@implooob) June 4, 2020
みずほの楽天出資、
マネリテある若者だけでワイワイやってる飲み会におじさんがノコノコ来て
「盛り上がってるねえ😄😄経験豊富なおじさんの話も聞いてほしいナ‼️みずほ証券のファンドラップやらない❓毎月分配型もあるよ😄
J-CoinPayもオススメ」みたいな感じで総スルーされやしないか心配なんだ僕
— 毎竹 (@every_bamboo) October 6, 2022
証券会社の各担当者に夏の自分のボーナスで買った銘柄を聞いてみた。大和、日興、みずほの担当者は何も買っていなかった。そういう会社に限って客には投信、投信、ファンドラップとうるさい。まず、自分で買ってからにしようね。
— チビだけど剣道 (@chibinakendo) July 28, 2020
みずほのファンドラップCM、おやじの退職金を運用したいけど守りたい→お聞きしますよで守るとは一言も言ってないのおもしろすぎ
— 主人公(名前入力必須) (@ukaremode) January 17, 2016
金融機関勤務の社員に何で運用するのか聞くのは、とても良いかもしれませんね。良いアイデアだと思います。
まとめ
みずほ証券が提供するファンドラップについて調べてきました。
ファンドラップ自体、筆者は魅力を感じませんが、やはり有名金融機関の名前のみで運用を決める人は少なくないでしょうね。そんな感想で締めくくりたいと思います。