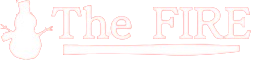藤野英人氏が設立したレオスキャピタルワークスは「ひふみシリーズ」を運用して2023年には東京証券取引所グロース市場に上場しています。
当サイトでも「ひふみシリーズ」については分析してきています。
関連
本日は外国株に投資をする「ひふみシリーズ」である「ひふみワールド」についてお伝えしていこうと思います。
関連記事)【ブログ随時更新】飛躍の2024年!今買いの一番儲かる投資信託銘柄はどれ?「安全」且つ「これから上がる」個人投資家が買うべき高利回りファンドを徹底調査!
ひふみワールドの特徴とは?
では「ひふみワールド」の特徴についてみていきましょう。
投資対象は日本以外の世界の株式
投資対象は名前をみても分かる通り、日本を除く世界各国の株式を投資対象としています。
「ひふみ投信」や「ひふみプラス」が日本株を投資対象としているので、棲み分けているということが分かりますね。
銘柄選択手法は「ひふみ投信」とおなじく、長期的な将来価値に対して、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄としています。
現金比率を最大50%まで引き上げることが可能
株式市場は下落する時は銘柄のファンドメンタルにかかわらず、全ての銘柄が下落していきます。
ひふみワールドは現金比率を最大50%まで引き上げることが可能です。

そのため、ちゃんとポジション調整ができれば暴落をある程度、回避することができる構造になっています。
あくまで、ちゃんと暴落を予想できたらの話ですけどね。
ファンドマネージャーは湯浅光裕氏
ひふみワールドの運用者は湯浅光裕氏となっています。

ホームページから抜粋した経歴は以下となります。
1990年ロスチャイルド・アセット・マネジメント入社、1993年日本株運用ファンドマネージャー就任、ロスチャイルドグループが海外で募集したユニットトラスト、年金資金の運用を担当する。
2000年、ガートモア・アセットマネジメント入社、中小型株ファンドの運用担当。
2003年、レオス・キャピタルワークス創業、取締役就任(現任)。運用本部長、ファンドマネージャーとして活躍、国内外資産運用業界について造詣が深い。参照:レオスキャピタル
経歴は非常に立派なのですが、残念ながら経歴先行型となっています。理由はリターンの項目で説明します。
ひふみワールドの構成上位銘柄
ひふみワールドの構成上位銘柄は以下となります。
1位のマイクロソフト、2位のフェラーリ、4位のアマゾン、6位のネットフリックスは多くの方が聞いたことがある銘柄ですね。
2023年10月からの構成上位銘柄の変遷は以下となります。価格の値動きで順番が変わっているものの長期保有していることが読み取れます。
| 2024年1月 | 2023年10月 | |
| 1 | MICROSOFT | FERRARI NV |
| 2 | FERRARI NV | MICROSOFT |
| 3 | Palo Alto | INTUIT |
| 4 | AMAZON | AMAZON |
| 5 | Dr. ING. | Palo Alto |
| 6 | NETFLIX | Dr. ING. |
| 7 | CBOE GLOBAL | DELL |
| 8 | NOVO NOORDISK | NETFLIX |
| 9 | EMERSON ELECTRIC | EMERSON |
| 10 | THE HERSEY CO | TETRA TECH |
ただ、他の銘柄も大型企業に分散しており、「ひふみ投信」と同じくインデックスと同様のリターンとなっていることが想定されます。(後述)
為替ヘッジは行なわず為替リスクを負う構造
為替ヘッジは行っていないので為替リスクを負っています。
ドル円やユーロ円などのリスクを負っていますが、多くのポジションはドル円なのでドル円を例に解説していきます。
ドル円が上昇すると基準価額は上昇し、ドル円が下落すると基準価額が減少します。
直近のドル円の推移をご覧ください。2022年に115円から152円まで円安が急激に進みました。2024年2月時点でも150円という水準になっています。
これは米国で1970年代ぶりに発生しているインフレに対応するために米国の中央銀行であるFRBが金利を引き上げている一方、日銀が緩和的な政策を行なっていることに起因しています。つまり金融政策が正反対であり、日米の金利差が拡大しているためドルの魅力が高まりドル高円安が進行してきたのです。

しかし、ここからは逆回転する確度が高くなっています。理由は今後景気後退となる可能性が高まっているからです。景気後退となると米金利は低下するので日米金利差は縮小します。さらに日本側の要因もあります。日本のインフレ率は高止まり続けており、日銀の金融政策が変更される確度が高まっています。
日銀がYCCを解除して長期金利を引き上げると日米金利差は縮小してドル円は逆回転を始める確率が高いです。ここからは為替という面で逆風が吹くことを考えておいた方が良いでしょう。
手数料(購入手数料/信託手数料)
手数料水準は以下となってます。
購入手数料:無料
信託手数料:年率1.6280%
購入手数料は低いのですが信託手数料は投資信託の中では高めに設定されています。
ただ、ひふみ投信と同じく買い付けから5年経過したら0.1%、10年経過したら0.25%の手数料が還元される信託報酬一部還元方式を敷いています。
「ひふみワールド」と「ひふみワールドプラス」の違いとは?
ひふみ投信も、「ひふみ投信」と「ひふみプラス」がありました。
両者は運用するマザーファンドは同じでリターンは同じなのですが信託報酬一部還元方式の有無や、最低投資金額の違い、直販と証券会社での販売の違いがありました。
「ひふみワールド」と「ひふみワールドプラス」の違いは以下となります。
| ひふみワールド | ひふみワールド+ | |
| 運用ファンド | ひふみワールドモデルナに投資をしているので投資方針、組み入れ銘柄、運用リターンは両者とも同じ | |
| 信託報酬 | 先述した信託報酬一部還元方式 通常:1.628%(税込) 5年経過:1.528% 10年経過:1.378% |
純資産に応じて信託報酬が低減 5000億円まで;1.628%(税込) 5000億円を超える部分:1.518%(税込) 1兆円を超える部分:1.353%(税込) |
| 最低申込金額 | 1000円以上1円単位 | 証券会社によるが100円から購入可能 |
基本的に大きな違いはないのですが、手軽に買えるのは「ひふみワールド+」の方ですね。
純資産はまだ2200億円という規模なので手数料は1.628%となります。
ひふみワールド+の運用実績!基準価額の推移とは?
では肝心の運用実績について移っていきたいと思います。以下は「ひふみワールド」の基準価額の推移です。
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 8.11% | 15.64% | -3.75% | 5.36% | 26.77% |
| 2022年 | -5.20% | -8.43% | -1.20% | 0.65% | -13.67% |
| 2021年 | 11.42% | 9.82% | -1.71% | 6.56% | 28.16% |
| 2020年 | -18.78% | 22.93% | 8.11% | 12.65% | 21.59% |
運用開始したのがコロナバブルの前の2019年というのが功を奏したのか堅調にみえます。ただ、2022、2023年は30%進んだ円安で大分下駄を履いています。
では次の項目でS&P500指数や全世界株式と比較しながら成績を紐解いていきましょう。
ひふみワールド+とS&P500指数と全世界株式を比較
ひふみワールドはインデックスに対してプラスのリターンを求めるアクティブ投信です。
→ アクティブ運用型とパッシブ運用型の投資信託のどちらが優れているのか徹底比較!インデックス投資は本当に最強なのか?
そのためインデックスに対しプラスのリターンを出していることが求められています。
以下は「ひふみワールド」と「S&P500指数(円建て)」と「eMAXIS全世界株式(円建て)」を比較したものが以下となります。
ひふみワールド
S&P500指数(円建て)
eMAXIS全世界株式(円建て)
「ひふみワールド」は全世界株式とS&P500に劣後してしまっています。わざわざ手数料を払ってアンダーパフォームです。
→ やめたほうがいい?評判だった「ひふみプラス」「ひふみ投信」の時代は終わった?まだ上がる?暴落の理由や今後の見通しを含め徹底評価!
「ひふみワールド」に投資するくらいなら、インデックスの方が良いのですが。
正直、筆者としてはインデックスに関しては、なかなか長期投資をするのが難しい投資先だと思っています。
なぜなら定期的に大きな暴落を被弾することになるからです。なかなか資産が半分になることは、常人には耐え難いですからね。
そこで筆者が投資をしているのがヘッジファンドです。ヘッジファンドは以下の通りインデックスよりも安定したリターンを暴落を回避しながら積み上げています。

以下で詳しくお伝えしていますのでご覧いただければと思います。
ひふみワールド+の掲示板での口コミや評判
では投資家のみなさんの評判や口コミを見ていきましょう。
Yahoo finance掲示板
利益所か私なんか何十万も損です、アメリカ経済の減速懸念も有り凄く心配です~損の少ない所で売った方が良いのではと思うのですが~?下がった所で買いたすのが良いのでしょうか?
Yahoo finance掲示板
21年2月に購入しましたがずっと横ばいで利益すら怪しいです。手数料考えたらマイナスですね
すぐに手放したいが余剰資金なので少し様子見です
Yahoo finance掲示板
2021年に銀行に勧められて購入以来下がりっぱなしです、銀行は長く持つように言いますが値動きが荒く大きな損が出るので不安です、長く持っていればよくなる保証が有るんでしょうか?
結構、横ばいが続いておりフラストレーションが溜まっている模様です。
ひふみワールド+の2024年以降の今後の見通し
重要なのは今後の見通しです。ひふみワールドは全世界株式とほぼ連動しているので、全世界株式の動向が重要となります。
現在2024年2月時点の経済状況を整理すると以下となります。
- 世界中のインフレは一旦落ち着いたが再び立ち上がってきている
- 景気後退の足音が近づいてきている
- 不動産価格を中心に崩れてきている
一時は落ち着きそうな様子をみせたインフレも粘着して、金融引き締めの長期化が意識されています。
金融引き締めが長期化すると、金利が高い水準で維持されるので2023年3月の地銀危機のように金融システムに異常が生じます。
そして、商業用不動産を中心にブラックスワンの火種も発生してきており、今後もしばらく厳しい展開が想定されます。
実際、現在と同じインフレが発生した1970年代は10年間、株式市場は横ばいで推移しました。
2020年代はインデックス的な動きをするファンドは低迷する可能性があるので注意が必要です。
関連記事)【ブログ随時更新】飛躍の2024年!今買いの一番儲かる投資信託銘柄はどれ?「安全」且つ「これから上がる」個人投資家が買うべき高利回りファンドを徹底調査!